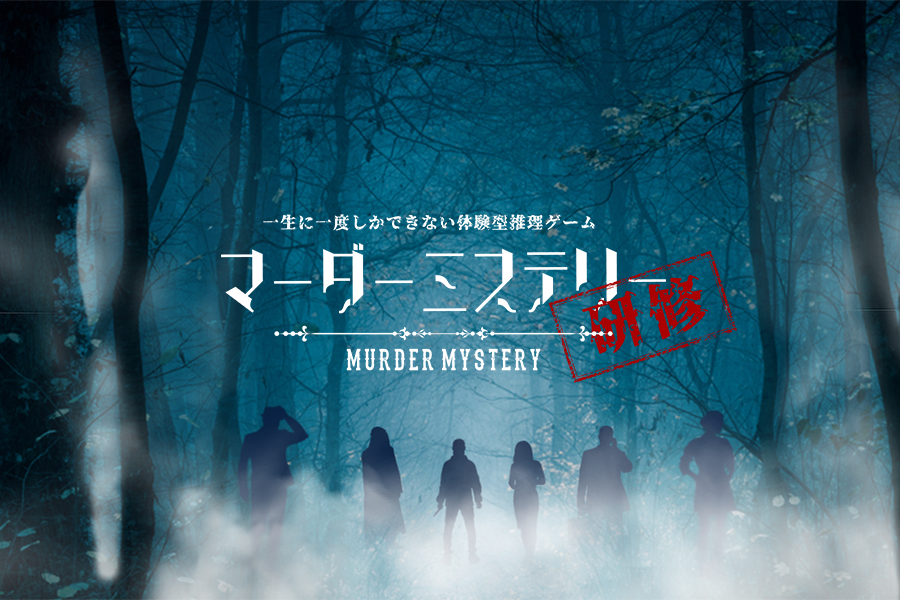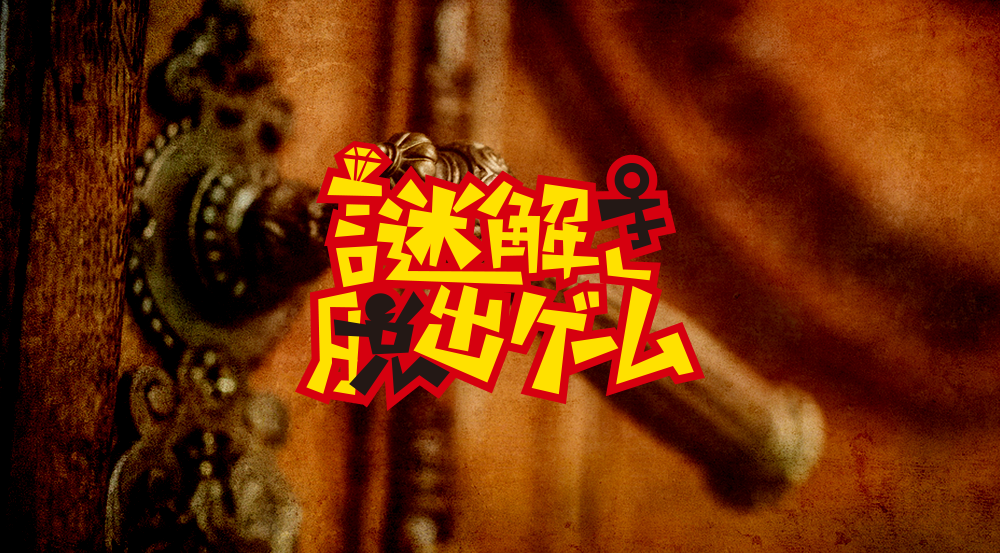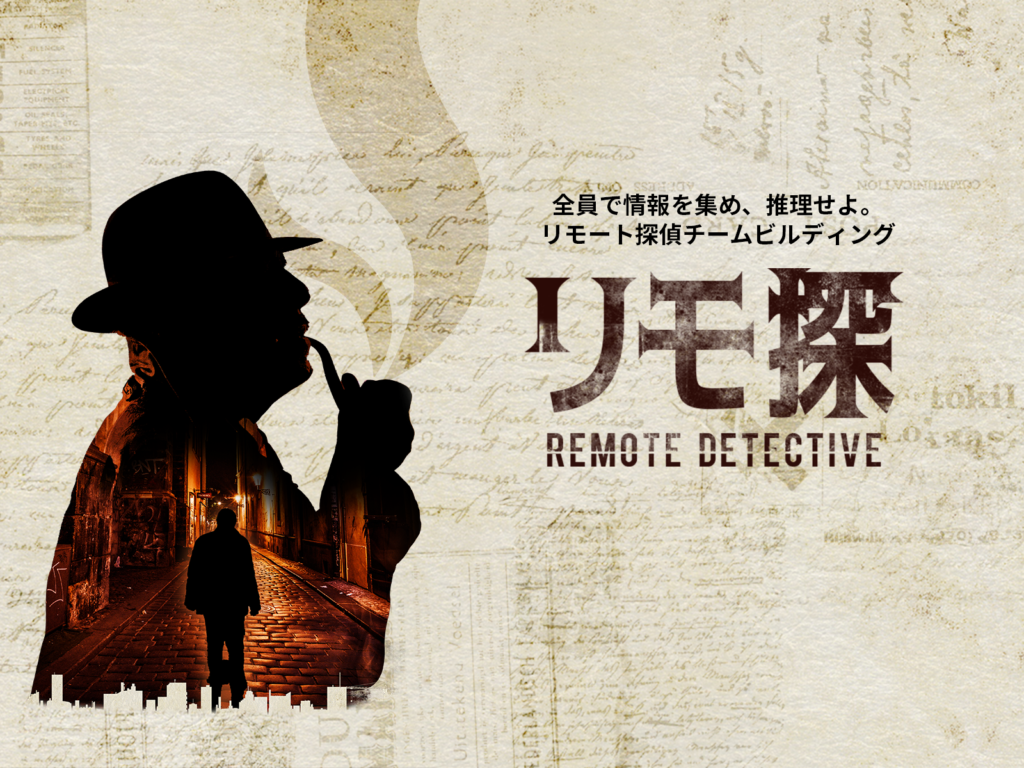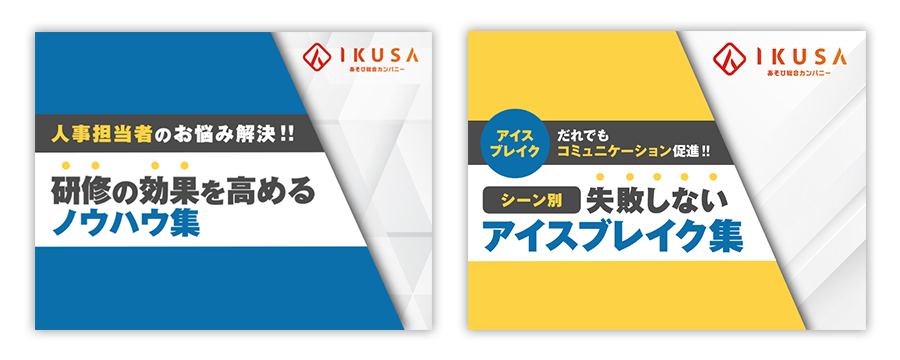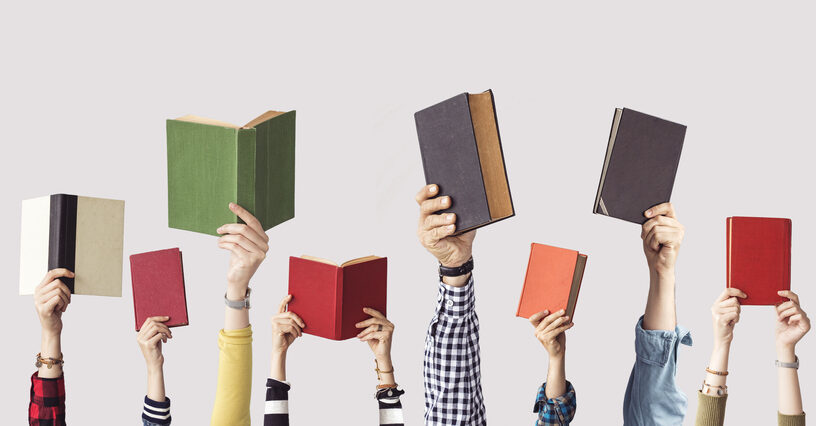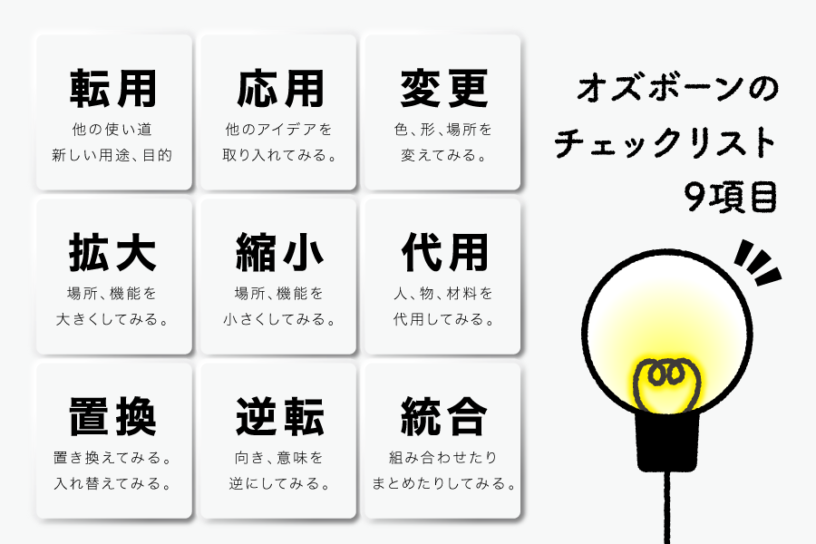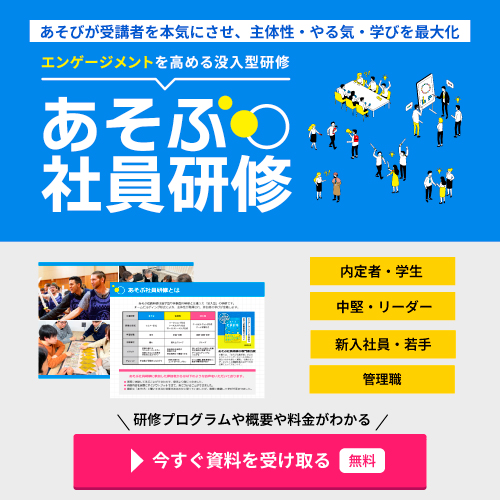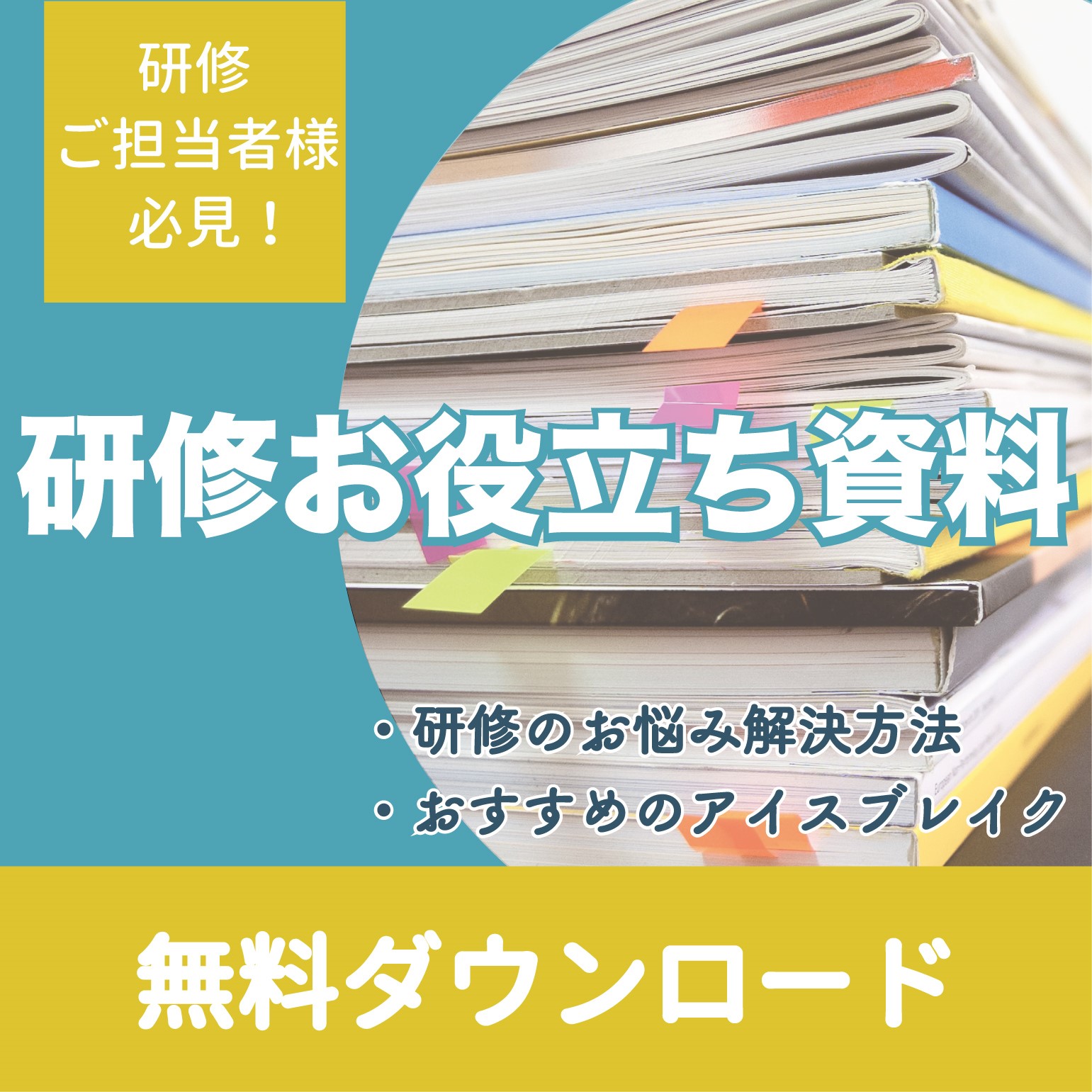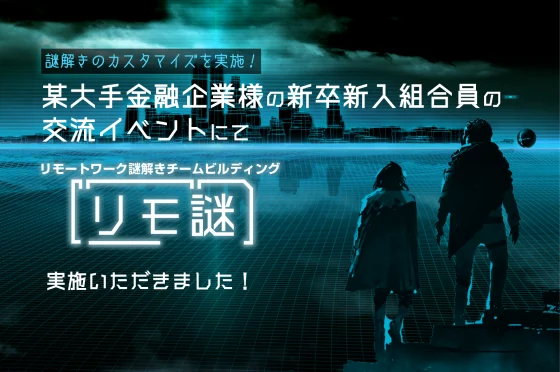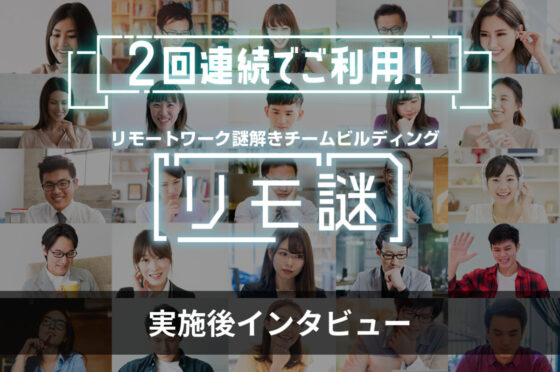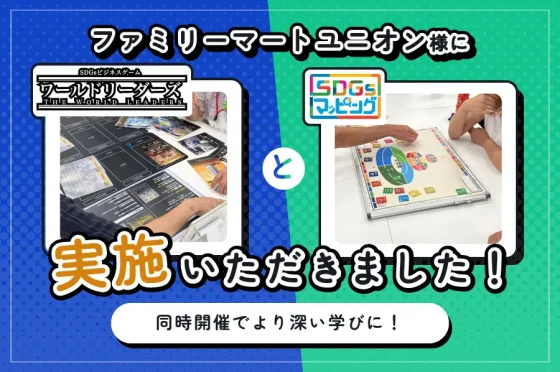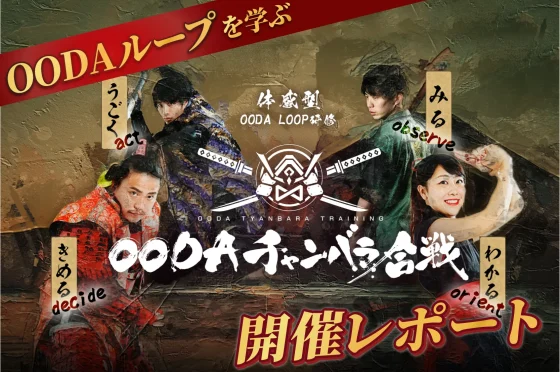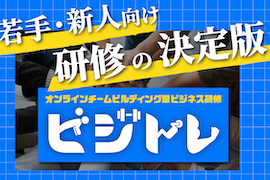- フレームワーク
- チームビルディング
人事担当者必見!効果的なチームビルディングを実践する具体的な方法

目次
組織活性化に向けた取り組みとして、コミュニケーションの促進やチームワークの向上などの効果が期待できる「チームビルディング」が注目されています。
しかし、チームビルディングにはさまざまな方法があり、どの方法が自社に適しているのか悩んでしまうケースも少なくないでしょう。
そこで本記事では、チームビルディングの方法について、「GRIPモデル」や「タックマンモデル」といったフレームワークを踏まえて解説します。
あわせて、チームが置かれている段階ごとのおすすめの方法も解説しますので、効果的なチームビルディングの実践に向けて、ぜひ参考にしてみてください。
研修にビジネスゲームを取り入れてチームビルディング。「ビジネスゲーム研修 総合資料」を無料で配布中
⇒無料で資料を受け取る
10秒で簡単ダウンロード「シーン別 失敗しないアイスブレイク集」
⇒無料で資料を受け取る
受講者のコミュニケーションを促すグループワーク「合意形成研修 コンセンサスゲーム」とは?
⇒無料で資料を受け取る
チームビルディングとは

チームビルディング(team building)とは、メンバーのスキル、能力、経験などを最大限に発揮し、目標を達成できるようなチームを作り上げていくための取り組みを指します。チームビルディングには、メンバー全員で参加できるゲームやアクティビティなどがあります。
チームビルディングを実践することで、コミュニケーションや相互理解の促進、チームワークの向上などの効果が期待できます。そして、チームを活性化できることから、多くの企業や組織がチームビルディングに取り組んでいます。
研修の企画にお困りですか? IKUSAの研修なら楽しくチームビルディングができます!
⇒IKUSAの研修資料を見てみたい
【属性別】チームビルディングの目的

チームビルディングの目的は、メンバーの能力やスキルといったそれぞれの強みを活かしてパフォーマンスを上げ、チームの目標を達成することにあります。
そのため、チームビルディングを実践する際には、その対象者の立場や役職などの属性ごとに適した目的を定め、企画していくことが望ましいといえるでしょう。
ここでは、対象者の属性におけるチームビルディングの目的をそれぞれ解説します。
こちらの記事では、チームビルディングの目的やメリットを紹介しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
チームビルディングの目的・メリットは?成功させるポイントを解説
新入社員
新入社員を対象としたチームビルディングでは、参加者に主体性を身につけてもらうこと、チームワークで物事に取り組む経験をしてもらうことが目的として挙げられます。
主体性やチームワーク(協調性)は、社会に出て間もない新入社員に身につけて欲しい姿勢です。そして、チームビルディングを通じて体感的に学んでもらうことで、今後の成長にも繋がります。
他にも、グループワークを通じてチーム内における役割分担やコミュニケーションを学ぶことで、仕事でも活用できるような能力を身につけることも目的としています。
こちらの記事では、チームビルディングの促進に繋がる研修を31選紹介しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
チームビルディングにおすすめの研修31選【室内・野外・オンライン】
中堅社員
本項における「中堅社員」とは、現場のメンバーをまとめるリーダーや主任、現場監督などの人材層を意味します。
中堅社員を対象としたチームビルディングでは、リーダーとしての部下の育成方法、チームの成果を最大限に上げるための目標への取り組み方など、現場社員のなかでも幅広いスキルを身につけることを目的としています。
管理職
部長や課長など、日本企業における「管理職」と呼ばれる人材層には、経営層と中堅社員の双方とのやりとりを仲介したり、チームのマネジメントを行ったりする役割が求められます。
管理職を対象としたチームビルディングでは、リーダーシップやマネジメント能力を身につける、部下への人材育成の取り組み方や社内外の関係者と接するコミュニケーション能力を向上させるなど、中堅社員よりも高度なスキルの習得を目的としています。
経営者・経営層
組織のトップに君臨する経営層を対象としたチームビルディングでは、実に多くの能力の取得が求められます。具体的には、トップとしての組織運営力、経営層としての視点や考え方、創造性や決断力、市場やニーズを先読みする能力などです。
また、トップ自らが動いて組織を牽制し統制する能力や、メンバー個々の意識を同じ方向に向かせるためのリーダーシップを身につけるなど、トップ層の人材として求められる人間力の醸成としてもチームビルディングを活用できます。
チームビルディングに活用できる「GRIPモデル」

チームビルディングを成功させるために必要な条件として、「GRIPモデル」と呼ばれるフレームワークがあります。GRIPモデルは、経営組織開発コンサルタントであるリチャード・ベックハード氏が提唱した効果的にチームビルディングを行うためのフレームワークです。
GRIPモデルでは、目標を達成するためのチームビルディングを行うには、「Goal(目的)」「Roles(役割)」「Interpersonal Relationship(人間関係)」「Process(段取り)」の4つの要素が欠かせないとされています。
チームビルディングを行う際には、GRIPモデルを意識して実施することが大切といえるでしょう。
Goal(目的・目標)
「Goal(目的・目標)」では、チームの目的や目標の明確化に向けた条件が満たされているかを確認します。
- チームの目標が明確で、メンバー全員に浸透しているか
- 目標に対して、メンバー全員が理解し賛同しているか
- 達成可能な範囲での目標設定ができているか
Roles(役割)
「Roles(役割)」では、メンバー個々の役割について掘り下げ、その役割を明確にするための条件が満たされているかを確認します。
- 目標に対して、メンバー各々の役割が明確になっているか
- 与えられた役割に対して、十分な能力やスキル、経験を持っているか
- 必要な人材や資源が不足している場合、人材育成や資源の補完ができるような施策が考えられているか
Interpersonal Relationship(人間関係)
「Interpersonal Relationship(人間関係)」では、メンバー同士の関係性や協調性に関係する条件が満たされているかを確認します。
- メンバー同士におけるコミュニケーションは円滑に行われているか
- メンバー同士の信頼関係は築かれているか
- チーム内で適切なフィードバックが行われ、そのフィードバックは適切な内容になっているかどうか
Process(段取り)
「Process(段取り)」では、目標達成に必要なタスクの整理や、仕事の段取りについて把握するための条件が満たされているかを確認します。
- 目標達成までのロードマップが明確化されているか
- メンバー各々の業務手順や、チーム内での連携方法が明確化されているか
- 各業務における意思決定の方法や問題発生時の対処法がチーム内で共有されているか
GRIPモデルにおけるそれぞれの条件を満たすことで、メンバーの能力や特性を最大限に活かし、目標を達成するための強いチーム作りへと繋がります。
チームビルディングを成功させるポイント3つ

GRIPモデルの条件を満たすことは非常に強固なチーム作りへと繋がります。加えて、次に紹介する3つのポイントをしっかりと押さえることで、チームビルディングをさらに成功へと近づくことができるでしょう。
無理な目標設定は避ける
チームビルディングでは、チーム目標の明確化が成功のポイントとなります。しかし、その目標が無理難題なものであるとメンバーのモチベーションが下がり、チームとしての特徴が機能しなくなる恐れがあります。
特に、チームの結成から間もない状況では、メンバー個々のモチベーションがチームビルディングに重要な要素になります。そのことから、無理難題な目標設定によるモチベーションの低下は避けるべきだといえるでしょう。
そのため、目標設定は達成可能な範囲内、かつ「ビジョンや方向性を共有するもの」とし、メンバーのモチベーションを刺激するための一つの要素として活用するのが望ましいといえます。
チームビルディングの進行をメンバー任せにしない
メンバーに主体性を持って活動してもらうことは、チームビルディングにとっても欠かせません。とはいえ、進行全てをメンバー任せにしてしまうと、それぞれがやりたいように進めるようになり、チームとしての機能が弱まってしまいます。
チームビルディングを成功させるには「チームが機能していること」が何よりも重要です。メンバーの主体性を尊重しつつも進行の全てを丸投げせずに、チームの進行役やまとめ役がリーダーシップを発揮して目標へ向けて導くことが大切といえるでしょう。
自社に適したチームビルディングを選ぶ
チームビルディングを行う際には、参加人数や確保できる時間、使える費用など、さまざまな要素を検討する必要があります。参加人数や時間によってチームビルディングの内容は異なることからも、チームや組織の状況に合ったゲームやアクティビティを選ぶことが重要です。
また、参加者の所属する部署や職種ごとに実務で求められる能力やスキルは異なります。そのため、個々の属性に合った能力やスキルを身につけられるようなチームビルディングの内容にすることが望ましいといえます。
参照:変化の時代に不可欠!チームビルディングのポイントと実践的な取り組み方法を紹介 | HRhacker
チームビルディングのやり方

チームビルディングにはいくつかのやり方が存在します。ここでは、そのなかでも代表的な4つのチームビルディングのやり方についてそれぞれ解説します。
ワークショップ
ワークショップとは「自主的な共同作業」です。参加者が自主的に発言したり、作業をしたりできる状況下で、チームに与えられた一つの目標を達成することを目的としています。
ワークショップを進めるには他の参加者とのコミュニケーションが必須になります。そのため、自然と自分の考えを発信したり、他者の意見を聞いて理解を深めたりといった行動が期待でき、チームビルディングの醸成へと繋がります。
ゲーム・アイスブレイク
複数人で楽しめるビジネスゲームやアイスブレイクは、チームビルディングとして有効に活用できます。特に、ビジネスゲームは簡単なルールにもかかわらず擬似的に経営体験ができる種類が多く、チームで協力しながらビジネスを学ぶことにも繋がります。
また、限られた時間内でのチームビルディングが求められる場合には、簡単なゲームを取り入れることで、会議やミーティング前におけるメンバーの緊張を解くことにも一役買います。
こちらの記事では、社員の仕事のモチベーションの向上に繋がる、チームビルディングゲームを10選紹介しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
チームビルディングはモチベーション向上に効果大!おすすめゲーム10選
こちらの記事では、おすすめのチームビルディングゲームを10選紹介しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
チームビルディングのメリットとは?タックマンモデルの解説&おすすめゲーム10選の紹介も
こちらの記事では、チームビルディングの促進に繋がるビジネスゲームを21選紹介しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。
チームビルディングにおすすめのビジネスゲーム23選!実施するメリットも解説
社内イベント
チームビルディングを目的とした社内イベントの開催は、多くの企業が実践しているやり方です。社内イベントの例としては、食事会、旅行、BBQ、キャンプ、合宿など、大人数でも参加できるようなイベントの実施が挙げられます。
他にも、全社員が集まるキックオフミーティングや総会を企画し、メンバー同士の親睦を深めるためのクイズ大会やスポーツ、レクリエーションなどを行うケースもあります。
アクティビティ
スポーツや運動など、体を動かす系のアクティビティは、チームで一緒に取り組むことによる一体感が生まれやすくなります。一つのアクティビティを通して、チームで苦楽をともにすることでチームワークが醸成され、メンバー同士の関係性も向上し、チームのコミュニケーションの活性化にも繋がるでしょう。
参照: チームビルディングとは?目的とプロセス、実施方法を具体的に紹介│Ritori
チームビルディングの5段階のプロセス「タックマンモデル」

チームビルディングにおける有名な理論として、心理学者のタックマン氏が提唱した「タックマンモデル」があります。タックマンモデルでは、チームの形成から解散まで、全部で5段階に分けられています。
各段階をチームが一丸となってクリアしていくことで徐々にチームが機能し始め、最大限のパフォーマンスが発揮できるようになるといわれています。このタックマンモデルの考え方を取り入れることで、より効果的なチームビルディングが行えるでしょう。
ここでは、タックマンモデルにおける各段階の解説と、段階ごとに適したチームビルディングの方法についてそれぞれ解説します。
タックマンモデル段階1: 形成期
形成期とは、一緒に活動するチームのメンバーが決まり、チームが形成されたばかりの状態を指します。形成期はチーム結成から間もないために、メンバー同士の相互理解が不十分かつチームの目標も不明瞭なため、チーム内には緊張感が漂う状態です。
そのため形成期では、メンバー同士の緊張をほぐしたり、相互理解を促進したりできるような、誰でも気軽に楽しめるチームビルディングが効果的といえます。
自己紹介系のゲーム
自己紹介系のゲームは必要な準備が少なく、短時間で気軽にできることが特徴です。形成期における初対面のメンバー同士の交流や相互理解の促進として、非常に有効なチームビルディングです。
通常の自己紹介以外にも、他者を紹介する「他己紹介」や、自分に加え、自己紹介を終えた人の名前も順番に言っていく「積み木自己紹介」など、自己紹介に「特別なルール」を設けたゲームを行うことで、よりメンバー同士の交流を図れるでしょう。
チェックイン
チェックインとは、会議や研修などの冒頭に行われるショートトークです。参加者一人ひとりが現在の気持ちやコンディション、会議や研修に対する思いなどを発表し、メンバー同士で共有していきます。チェックインを行うことで、メンバー各々の思いや状態を把握し、お互いを気遣ったり、コミュニケーションを円滑にしたりする効果が期待できます。
グッド&ニュー
グッド&ニューとは、ここ最近で自分が嬉しかったこと、感動したことをメンバーへ伝えるゲームです。グッド&ニューで発表することは、どんなにささいなことでも構いません。お互いの発表を聞くことで、メンバーの意外な一面を知ることができ、簡単ながらも親睦を深めることへと繋がります。
やり方
- 最初のメンバーが「良かったこと」または「新たな気づき」について話す
- 話し終わったら他のメンバーは拍手をする
- まだ話していないメンバーを指名して、次はその人が話し始める
- 全員が話し終わるまで繰り返す
マシュマロチャレンジ
マシュマロ、パスタ、紐、テープ、はさみを使ってタワーを作り、タワーの頂上にマシュマロを置きます。勝利条件は「自立可能でもっとも高いタワーを作ったチーム」です。協力してタワーを作るためのチームワークの向上、自然なコミュニケーションの促進など、楽しみながらチームビルディングが体感できるゲームです。
やり方
- 乾燥パスタ、マシュマロ、テープ、ひも、はさみを用意する
- チームを作り、作戦会議をする
- 制限時間内に最も高いタワーを作ったチームが勝ち
タックマンモデル段階2: 混乱期
混乱期は、チームの目標が決まり、業務やプロジェクトが進み始めた段階です。混乱期では、メンバー個々の価値観や考え方が違うことが原因で意見の対立が起こりやすいという特徴があります。また、メンバーの意識や関心も、本来やるべき業務やプロジェクトではなく、お互いの行動や発言に向いてしまう傾向が強く現れます。
混乱期を乗り越えるためには、意見の対立を避けるのではなく、お互いが意見を言い合える機会を作り、議論を通じて相互理解を深めることが重要です。メンバーの考え方や価値観を知ることで、チームが一つにまとまり、次の段階である「統一期」に移行することが可能となります。
混乱期では、メンバー同士の会話やコミュニケーションを促進したり、相手の価値観や考え方を理解できたりするチームビルディングが有効です。
コンセンサスゲーム(ジャングルサバイバル・帰宅困難サバイバル)
コンセンサス(合意形成)ゲームとは、物語を通して「合意形成を得るためのプロセスや要点」を体感できるゲームです。多くのビジネスシーンで求められる合意形成ですが、それを成功させるには、対話力や傾聴力、コミュニケーション能力など、実にさまざまな能力が求められます。
やり方
- 予期せぬ問題が発生する
- 対処法をまずは個人で考える
- 次にチームで対処法を考える
- 専門家の結論と比べ、自分のチームの対処法の妥当性を確認する
コンセンサスゲームでは、これらの能力が必要な場面を体感でき、能力を身につけることで、より効果的なチームビルディングを行うことが可能となります。
株式会社IKUSAでは、クルージング中にジャングルに遭難するというストーリーの「ジャングルサバイバル」、災害後の都市部を舞台にした「帰宅困難サバイバル」といったコンセンサスゲームを提供しています。各ゲームでは、物語や参加者のシチュエーションが異なるため、参加者の属性に合ったゲームを選ぶことがおすすめです。オンラインとリアル、どちらにも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
ディベート大会
ディベート大会とは、お題に対して肯定派と反対派の2つに分かれて討論し、聴衆からより多くの賛成数を得たチームの勝利となるゲームです。相手チームを論理的に説得するためには、相手の考えや立場に対する理解や、チーム内での意見交換が重要なポイントとなります。相手チームの説得に向けてチーム内で話し合うことで、チームワークの向上や相互理解の促進に繋がるでしょう。
マーダーミステリー研修
マーダーミステリーは体験型の推理ゲームです。誰が犯人で、誰と協力すればよいのかわからない、互いに疑い合うというシチュエーションで、自分に与えられた役割を演じながら目的達成を目指します。
やり方
- 台本に従って物語を進める
- 犯人は犯人であること、それ以外は自分の秘密を隠しながら情報交換していく
- 事件解決を目指し推理する
マーダーミステリー研修を行うことで、社会人基礎力といわれる考え抜く力、チームで働く力、前に踏み出す力だけではなく、交渉力も身につきます。
マーダーミステリー研修の資料ダウンロードはこちらモンスタービルディング
モンスタービルディングは、元になったモンスターの一部分だけが描かれた情報カードを一人一枚配布し、協力しながらモンスターを作っていくゲームです。
ルール上、相手のカードは確認できず、口頭でしかカードの情報共有ができません。また、各々がさまざまな角度から見たモンスターの情報しかわからないため、クリアするにはメンバー全員が発言をし、正確な情報共有が求められます。
ゲームを通じて、その人の立場によって視点や考えていることが異なること、口頭のみでの情報共有は簡単ではないこと体感でき、チームビルディングの中でも特に相互理解の大切さを学べるゲームです。
タックマンモデル段階3: 統一期
統一期は、メンバーが各々の意見を出し合うことでお互いの意見や考えに対する理解が深まり、混乱期を乗り越え、チームとしての基盤が構築されていく段階です。統一期になると、チームの目標とその達成に向けたメンバー各々の役割が明確になり、チームとしてのまとまりが現れます。
統一期から次の段階である「機能期」へとステップアップするためには、各メンバーの個性を活かす役割分担や、チーム目標を達成するための明確なプロセスが必要になります。チームビルディングを通じて、メンバーの個性を見つけ、それを活かしていくことが求められます。
統一期では、チームで一丸となって取り組まなければクリアできないようなゲームやアクティビティを行うことで、さらなるチームビルディングの醸成へと繋がるでしょう。
リモ謎
リモートワークでもチームビルディングができる、参加型の謎解き脱出ゲームがリモ謎です。ビデオチャット通話を使ってチームで協力しながら謎を解き、指定された空間からの脱出を目指します。出題される謎は、チームで協力しなければ解けないような謎であり、メンバー同士が自然とコミュニケーションを図れる状況が作れることも特徴的です。
やり方
- オンラインのビデオチャットツールを用意する
- チームで協力をしながら物語にそった謎を時間制限内に解く
- 危機的状況からの脱出を目指す
リモートワークによって、社内コミュニケーションが希薄になってしまった組織やチームにおすすめのチームビルディングといえるでしょう。
謎解き脱出ゲーム
謎解き脱出ゲームとは、参加者自身が物語の主人公となり、決められた条件下で与えられた謎を解くことで物語のクリアを目指す体験型アクティビティです。
やり方
- 制限時間や閉じた空間の中で与えられた謎を解く
- 全ての謎が解けたらゲームクリア
チームで協力して謎を解くためのコミュニケーションやリーダーシップが求められ、チームとして明確な目標のクリアに向けた取り組みに繋がることからも、統一期におけるチームビルディングとしての効果が期待できるゲームです。
サバ研
サバ研は、サバイバルゲームにチームビルディング要素を取り入れたゲームです。アメリカの軍隊や企業で採用されている「OODA LOOP」と呼ばれるフレームワークが取り入れられ、勝つための意思決定プロセスを高速で回すことにより、瞬時に最適な判断を下せる力を身につけることを目的としています。
勝利のための戦略性やチームワークなど、チームビルディングに求められる能力を楽しみながら学べるゲームとして有効に活用できるでしょう。
リモ探
リモ探は完全リモートで実施できるリモート探偵チームビルディングです。それぞれが得た情報をチーム内に持ち寄り整理しながら、事件を解決していきます。
やり方
- チーム分けをする
- それぞれ担当のグループに行き情報を取得
- その得た情報を自分のチームに持ち帰り、チームメンバーに伝える
- 集めた情報を整理し、推理していく
チーム内で教え合い、情報共有することで学習効果が高まるというジグソー法をもとに作られました。専門MCを配置されるので世界観に没入できます。くわえてフォロースタッフのサポートがあるので、大人数での開催でも安心です。
タックマンモデル段階4: 機能期
機能期とは、チームにおけるメンバーそれぞれの役割が機能している状態のことを指します。機能期にまで達すると、主体的に行動できメンバー同士のサポートも期待できることから、チームとしての成果や結果が現れ始めます。
この機能期の状態を持続するには、チームリーダーによるメンバーへのサポートや、チームワークをさらに高めるアクティビティの実施など、チームビルディングを醸成し維持できるような対策が求められます。
加えて、チームで成功体験を共有することによりさらなる結束力が生まれ、メンバーのモチベーションの向上にも期待ができます。機能期の状態を持続させるためにも、メンバー同士で協力し合え、チームワークを高められるアクティビティは非常に効果的といえるでしょう。
チャンバラ合戦–戦IKUSA-
チャンバラ合戦–戦IKUSA-は、当たっても痛くないスポンジの刀と、「命」と呼ばれるボールを使った対戦型アクティビティです。肩につけた命を刀で切り落とし、生き残った人数をチームで競い合うという簡単なルールで、年齢や性別問わず誰でも楽しめるゲームとなっています。
やり方
- 参加者の肩に命(ボール)を付ける
- スポンジの刀を使って相手の命を切り落とす
- 最終的に生き残った人数をチームで競い合う
その一方で、一定レベルの戦略性も求められることからも、チームワークや役割分担、コミュニケーションといった、チームビルディングに欠かせない能力の醸成も期待できます。年齢や世代の影響が少なく、参加者の属性を問わずに楽しくチームビルディングが実践できるでしょう。
おうち防災運動会
おうち防災運動会は、オンラインで防災体験ができる新感覚の防災ゲームです。チームごとに分かれて競争を楽しみながらも、生活をするうえで必要な防災知識についての理解を深められます。
チームプレイやコミュニケーションの促進など、オンライン特有のチームビルディング要素も組み込まれ、楽しいだけではなく、日常に役立つ知識を得られるチームビルディングとしても有効に活用できます。
SDGsビジネスゲーム ワールドリーダーズ
SDGsビジネスゲーム ワールドリーダーズは、企業のためにつくられた企業経営を体験できるSDGsビジネスゲームです。各チームは企業として戦略を立て、労働力や資本を使って利益を競います。チームで戦略を練り、その場に合った選択をしていくため、それぞれが主体性を発揮しながら、チームビルディングを高めることができるでしょう。
やり方
- いくつかのチームに分かれる
- 企業として戦略を立て、労働力や資本で利益を上げる
- 最も多くの利益を上げたチームを優勝とする
BBQ・キャンプ
BBQやキャンプは事前準備や役割分担などが必要になるため、メンバー同士のコミュニケーションが促進されます。メンバーと一緒に食事をしたり、自然の中でゆっくりすることでリラックス効果が期待できたりと、ゲームやアクティビティとは違った形でのチームビルディング効果が得られるでしょう。
スポーツ大会
スポーツには、チームワークの向上やコミュニケーションの促進、役割分担などの要素が求められ、チームビルディングとしても大きな効果が期待できます。スポーツのなかでもチームプレイが求められるものがチームビルディングに適切です。サッカーやバレーボールなどのさまざまなスポーツが選択肢として挙げられ、チームメンバーの属性に合ったスポーツを選ぶことで効果的なチームビルディングが期待できます。
タックマンモデル段階5: 散会期
散会期は、プロジェクトの終了やメンバーの異動などにより、チームとしての一つの活動が終わる段階です。散会期にまで達したそれぞれのメンバーは、今回のチームでの経験を活かして、次のチームやプロジェクトに向けて動き出すことができるでしょう。
各メンバーの行動を称賛したり、互いに感謝を伝えたりすることで、自信を持って、新たなチームでの活動に挑むことへと繋がります。
まとめ

チームビルディングにはさまざまな方法があり、自社のチームや組織に合った方法を選ぶことがチームビルディングを成功させるポイントです。
チームビルディングを検討する際には「GRIPモデル」や「タックマンモデル」を取り入れることで、適切なチームビルディングの選定へと繋がります。ぜひ本記事の内容を参考に、効果的なチームビルディングを実践してみてください。
研修やチームビルディングイベントの企画にお悩みの方必見!「ビジネスゲーム研修 総合資料」では、謎解き、推理ゲーム、サバイバルゲームなどを活用したユニークな研修を事例とともにご紹介しています。
⇒無料で資料を受け取る
合意形成のプロセスを楽しく学べる「合意形成研修 コンセンサスゲーム」。オンライン、対面のどちらでも実施が可能です。ゲームの詳細や具体的な事例は下記の資料でご確認ください。
⇒無料で資料を受け取る
研修の満足度向上を実現する「研修お役立ち情報」とは?
失敗しない研修のノウハウを公開!
目次

ビジネスゲーム研修.comでは、研修のお役立ち情報や、体験型研修の事例をご紹介しています。オンライン研修やチームビルディング研修をお探しの方は、ビジネスゲーム研修.comにお任せください。