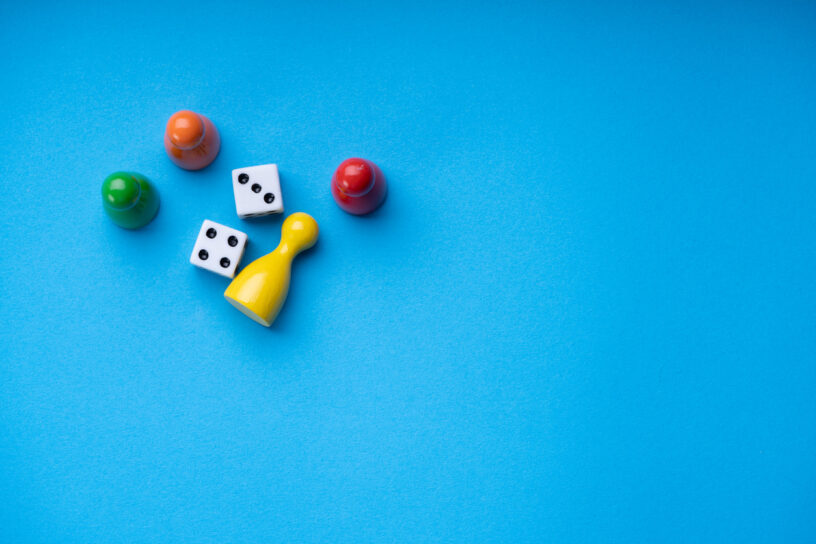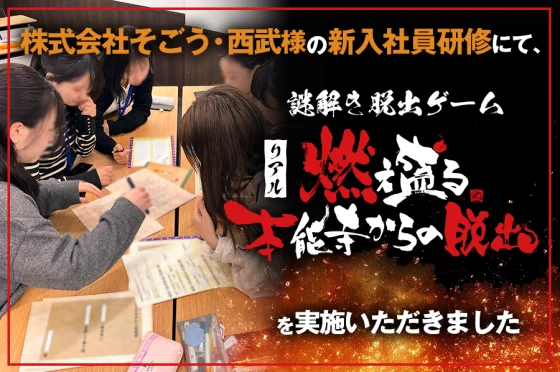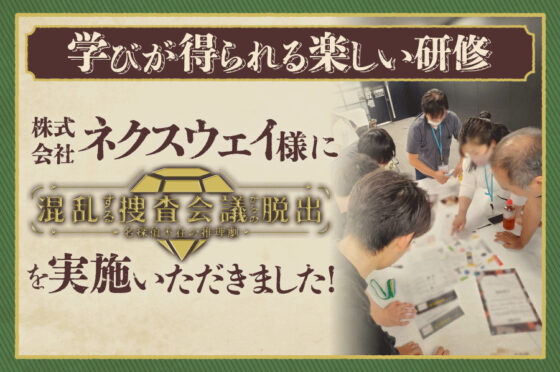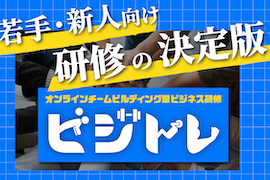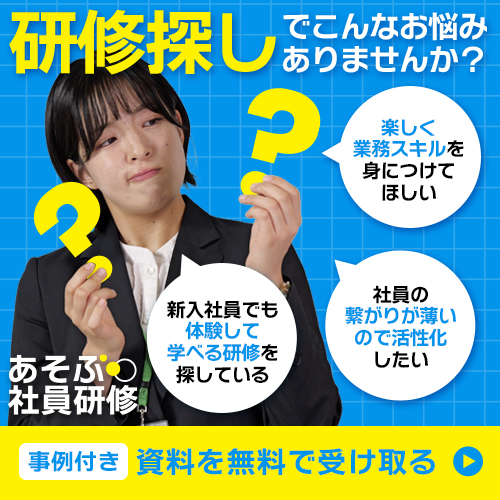- フレームワーク
- 研修ノウハウ
- チームビルディング
ロジックツリーとは?メリット・作り方・ツールを紹介


目次
ロジックツリーとは、問題解決や意思決定のプロセスを構造化して視覚的にわかりやすく書き出すフレームワークです。明確に整理できるため、全体像を把握しやすいことが特徴です。
本記事では、ビジネスシーンで役立つロジックツリーの概要のほか、メリットや作り方、ツールを紹介します。
退屈な研修はおしまい。ゲーム形式で楽しく学びを促進
⇒ビジネスゲーム研修 総合資料を受け取る
ゲーム・講義・ワークを組み合わせたアクティブラーニングで学びを深める研修
⇒あそぶ社員研修 総合資料を受け取る
ロジックツリーとは

ロジックツリーは、問題解決や意思決定のプロセスをツリー状に構造化し、視覚的にわかりやすく導き出すフレームワークです。主題となる問題や目標などをツリー状の頂点とし、原因や解決策をツリー状に分岐させていく図を作成します。
ロジカルシンキングとロジックツリーの関係
ロジカルシンキングは矛盾・破綻のない筋道を立て、結論を導き出す思考法です。ロジカルシンキングはビジネスシーンでも基礎的なビジネススキルと位置づけられており、新卒社員や若手社員を対象とした研修が多くの企業で実施されています。
ロジックツリーを作成する際には、矛盾や破綻のない筋道を立てて思考するロジカルシンキングが必須となります。
フィッシュボーンとロジックツリーの違い
ロジックツリーとよく似たフレームワークにフィッシュボーンがあります。フィッシュボーンとは、ロジックツリーと同様に、主題となる問題や目標を頂点(魚型の頭部)に置き、魚の骨のように書き出していきます。フィッシュボーンは、フィッシュボーンチャート(特性要因図)とも呼ばれます。
フィッシュボーンは、階層ごとの要素を並記するため、モレ・ダブリが起こりにくく、比較検討がしやすいという特徴があります。一方、ロジックツリーは、要素ごとに枝分かれして書き出すことができるため、より詳細に分析・検討がしやすいことが特徴といえます。
ロジックツリーを活用するメリット

ここからは、ロジックツリーを活用するメリットを紹介します。
モレ・ダブリを防ぎやすい
ロジックツリーでは、要素ごとに関連する要因を書き出すことができるため、モレ・ダブリを防ぎやすいという特徴があります。モレ・ダブリを避けることで、論理的かつ正確に要素を分析することができます。
問題の深堀りや可視化がしやすい
ロジックツリーは原因を分解していく手法であるため、問題を深堀りして詳細に分析することができます。詳細な分析が可能となることで、問題の原因を特定し、有効な施策を検討しやすくなります。また、問題に対する原因を可視化できるところもロジックツリーの特徴といえます。
解決策の優先順位がつけやすい
ロジックツリーを活用することで、問題解決における優先順位をつけやすくなります。効率よく有効な施策を講じることができるようになり、短期的な問題解決を目指せます。また、問題解決のための費用・コストや人的リソースを効率的に活用できるようにもなります。
ロジックツリーの作り方

ロジックツリーには「Whatツリー」「Whyツリー」「Howツリー」という3つの種類があります。
ここからは、3種類それぞれのロジックツリーの作り方を紹介します。
Whatツリーの作り方
「Whatツリー」は、要素分解ツリーとも呼ばれます。ある要素を設定し、そこから細かい要素へと分解していきます。たとえば、「国内旅行」を主題とした場合、まず行先を「西日本」と「東日本」に分解。そこから「西日本」の場合は、「九州・沖縄」「四国」「中国」「近畿」というように分解していきます。
「Whatツリー」は、網羅的に要素を把握したいときに役立ちます。Whatツリーでモレ・ダブリなく書き出すことで、適切な要素を見つけ出すことができます。「Whatツリー」は、顧客や市場を分析する際に有効です。
Whyツリーの作り方
「Whyツリー」は、原因追求ツリーとも呼ばれます。ある問題の原因を追求する際に用いられるロジックツリーであり、根本的な原因を探りたいときにおすすめです。
例えば、「なかなかお金が貯まらない」という問題を主題に設定する場合には、「出費が多い」、「収入が少ない」などの原因に分解することができます。さらに分解していくことで、お金が貯まらない根本的な原因が見えるでしょう。
Howツリーの作り方
最後に紹介する「Howツリー」は、問題解決ツリーとも呼ばれます。「Whyツリー」が問題の根本的な原因を探るのに対し、「Howツリー」は問題の解決策・改善策を探すことを目的として用いられます。
例えば、「新商品の売り上げを伸ばしたい」という問題を主題に設定する場合には、「告知する」、「価格を下げる」などに分けられます。ただ、これだけではあいまいであり、具体的な方法まではわかりません。そのため、「告知する」から「SNSで紹介」、「テレビCMを作って放映」などの具体的な解決策を書き出すまで続ける必要があります。
なお、「Howツリー」を活用した例として、「KPIツリー」があげられます。目標(KGI)を達成するためのプロセス・要素(KPI)を確認することができます。
ロジックツリーを作る際のポイント・注意点

ここからは、ロジックツリーを作成する際のポイントや注意点を紹介します。
MECE(モレ・ダブリなく)を守って作成する
ロジックツリーを作る際は、「MECE(ミーシー)」が重要です。「MECE」とは、「Mutually(お互いに)」「Exclusive(重複せず)」「Collectively(全体として)」「Exhaustive(漏れがない)」の頭文字を組み合わせた言葉。「モレなく、ダブリなく」とも訳されており、ロジックツリーを作るうえで重要となります。
ただし、ロジックツリーで設定した問題によっては別の要素でダブリが発生する場合があります。各要素を正確に分析するために必要であれば、ダブリがあっても問題ありません。
原因と結果を同一視しない
ロジックツリーを作る際は、結果と原因を同じように捉えてはいけません。それぞれ別のものとして区別する必要があります。
ロジックツリーの場合、頂点に近い要素が結果、それに紐づく要素が原因という関係になります。結果を分解して原因を見つけ出し、深掘りしながらさらに原因を見つけ出すということを繰り返してロジックツリーを作っていきます。
頂点から最も遠い要素が行動につながるように展開する
ロジックツリーを作る際は、頂点から最も遠い要素が行動につながるように展開することが重要です。「Howツリー」で取り上げた「新商品の売り上げを伸ばしたい」という例であれば、「告知する」だけでは具体的な行動が見えません。しかし、「オウンドメディアで紹介」や「テレビCMを作って放映」まで分解すれば、「告知する」よりも具体的な行動内容がわかります。具体的な行動が明確になるまで分解することが重要です。
要素の順序も大切
ロジックツリーは、思いついたものを書けばいいというわけではなく、要素の順序も大切です。分解するうえで要素をどの順序で書き出せばいいのか意識しながら作っていくことで、縦のつながりも見え、原因や解決策がイメージしやすくなります。
ロジックツリーにおける順序の関係性として、「フロー・ストック」や「イン・アウト」などが挙げられます。「フロー・ストック」はそのときだけの単発要素(フロー)か、継続する要素(ストック)かで分けるというものです。「イン・アウト」は内的要素(イン)か外的要素(アウト)かで分けます。
テンプレートを活用する
ロジックツリーの作成に時間がかかる場合には、テンプレートを活用してみましょう。ロジックツリーは一般的なツールを活用して簡単につくることができ、テンプレートが提供されている場合もあります。
ロジックツリーが作成できるツール

最後に、簡単にロジックツリーが作成できるツールを紹介します。
Excel
ビジネスでよく使われるツールである「Excel」ですが、ロジックツリーを作ることができます。また、「Excel」に搭載されている「Smart Art」で、マトリックス図やピラミッド図などを作成することも可能です。
まず「挿入」から「Smart Art」を選択し、そこから「階層構造」を選びます。次に「階層構造」の中から横方向に展開する階層を選択します。ロジックツリーの原型を用意することで、簡単に作成できます。
PowerPoint
「Excel」と同様にMicrosoft Officeの1つである「PowerPoint」でもロジックツリーが作れます。
「PowerPoint」は「Excel」よりもデザイン性に優れたロジックツリーを作成することができ、プレゼンテーションで活用したい際におすすめです。「PowerPoint」も「Excel」と同様に、「Smart Art」で「階層構造」を選択することでロジックツリーを作成できます。
Lucidchart
「Lucidchart」は、簡単な操作でロジックツリーが作成できるツールです。テンプレートが豊富なことが特徴といえます。パソコンに限らず、スマートフォンやタブレットなどからもアクセスできることから、外出先で編集することもできます。
また、「Excel」や「PowerPoint」などの外部ツールとの連携が可能です。「Excel」や「PowerPoint」であればエクスポートに対応しています。
XMind
「XMind」はマインドマップを作成することに特徴のあるツールですが、ロジックツリーを作ることも可能です。無料で使うこともできるうえに、テンプレートが用意されているため、簡単にロジックツリーを作成可能です。有料版であれば、「Word」や「PowerPoint」にエクスポートできます。
まとめ
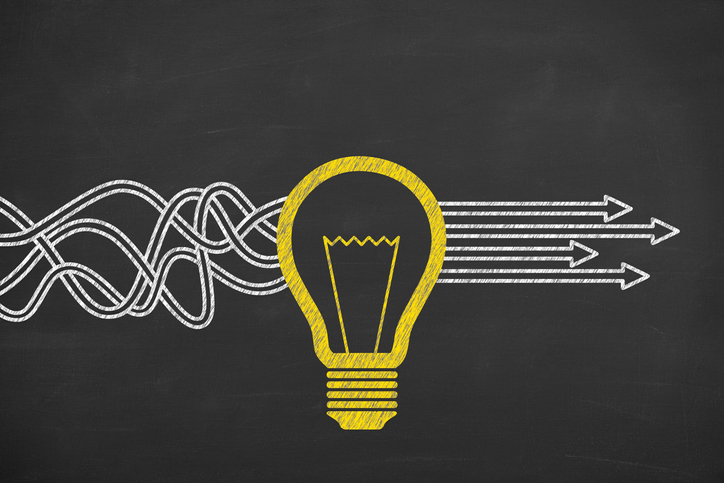
ロジックツリーを作成することで、問題の原因や解決策を導き出すことができます。有効に活用するには、思考法の基礎となるロジカルシンキングを身につけることが大切です。
退屈な研修はおしまい。ゲーム形式で楽しく学びを促進
⇒ビジネスゲーム研修 総合資料を受け取る
ゲーム・講義・ワークを組み合わせたアクティブラーニングで学びを深める研修
⇒あそぶ社員研修 総合資料を受け取る
目次

ビジネスゲーム研修.comでは、研修のお役立ち情報や、体験型研修の事例をご紹介しています。オンライン研修やチームビルディング研修をお探しの方は、ビジネスゲーム研修.comにお任せください。