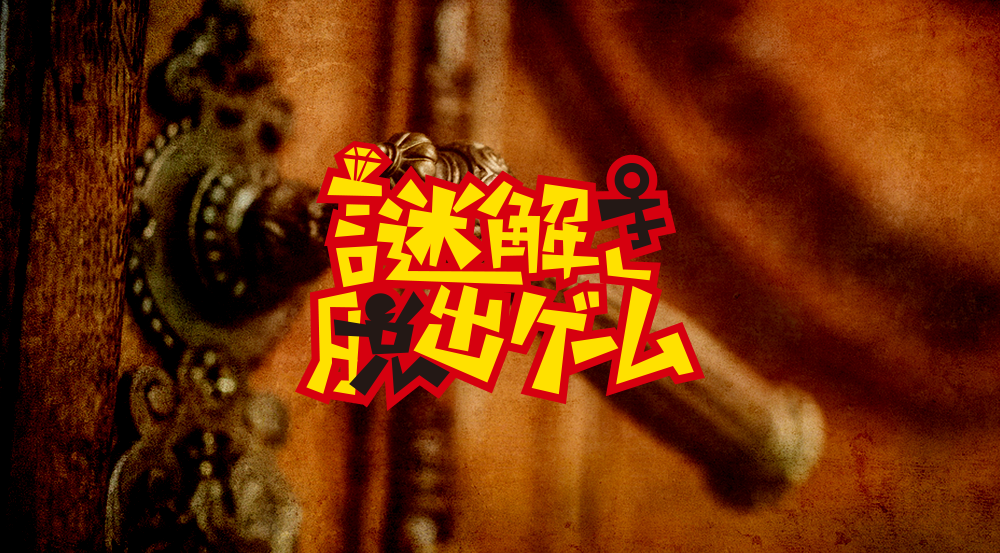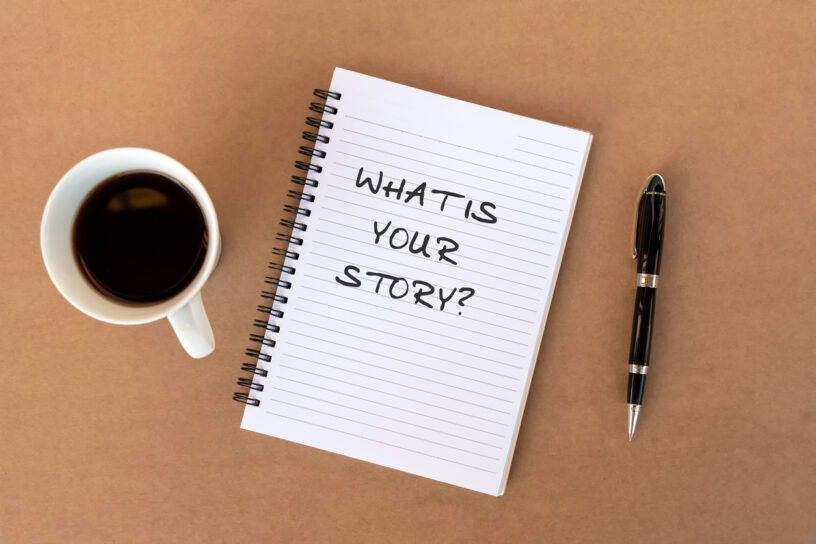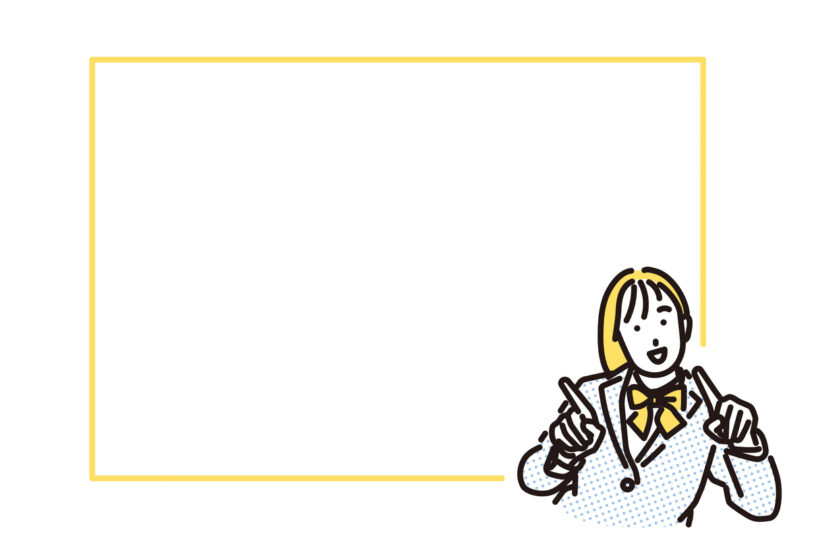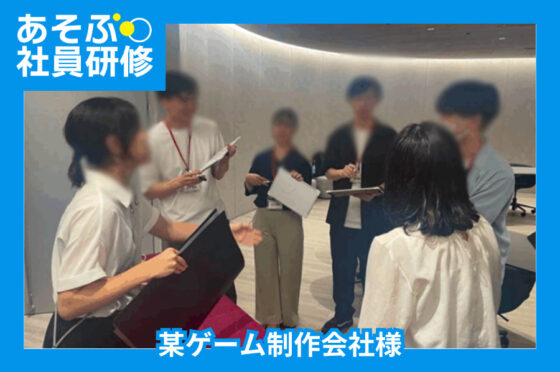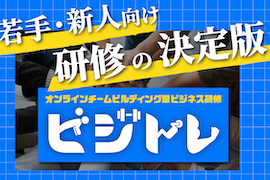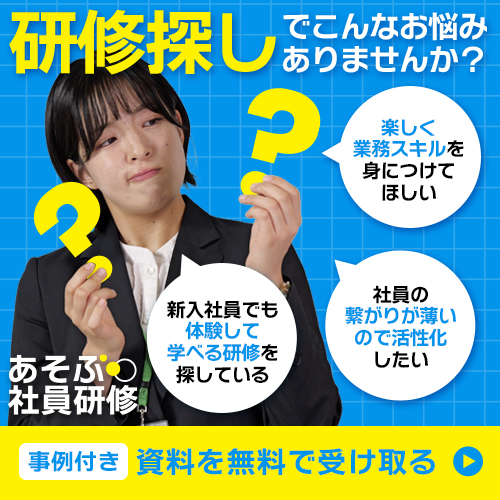- フレームワーク
- チームビルディング
- 研修ツール
タックマンモデルとは?活用方法・アクティビティ17選


目次
会社の離職率低下や業績向上のための施策として、チームビルディングが注目されています。
本記事では、タックマンモデルの概要、チームビルディングを目的とした活用方法、チームビルディングゲーム10選を紹介します。
タックマンモデルとは

タックマンモデルとは、組織・チームの状態ごとに5つの段階を具体的に表したチームビルディングの主要なモデルの1つです。
タックマンモデルは下記の5段階に分類されます。
- 形成期(組織・チームの初期段階)
- 混乱期(意見の対立・ぶつかり合いが起こる段階)
- 統一期(相互理解が深まって効率的に連携できる段階)
- 機能期(リーダーが不在でも各々が共通の目標に向かって機能する段階)
- 散会期(組織・チームが終了する段階)
タックマンモデルに基づいて組織・チームを分析することで、現在の状態がわかり、機能期を目指すために必要な施策がイメージしやすくなります。
チームビルディングを実現するには、タックマンモデルにおける混乱期から統一期に至ることが重要です。意見が対立したり、ぶつかり合ったりする時期があっても、それを乗り越えることで各々が機能するチームに近づくことができます。
チームビルディングの概要
チームビルディングとは、チームの全員が共通認識をもって目標に向かい、各々の強みを生かして効率的に連携することで成果を最大化させることができるチームづくりを指します。
チームビルディングを行うことで、メンバー間のコミュニケーションの活性化をはじめ、良い人間関係の形成、信頼感や結束力の向上、生産性の向上、離職率の改善などの効果が期待できます。
タックマンモデルの5段階

タックマンモデルは、心理学者のブルース.W.タックマンが1965年に提唱したチームビルディングに関するモデルです。
組織・チームの結成から解散に至るまでの組織形成の過程を5段階に分け、それぞれの特徴を定義づけています。「形成期」「混乱期」「統一期」「機能期」「散会期」の各段階について説明します。
形成期
「形成期」は、組織・チームができたばかりの段階です。
相互理解が浅く、目標・目的が統一されていない状態です。形成期では、メンバーの心理的安全性が低いことで意見を率直に伝えることができず、不安や緊張感がチーム内にあることが特徴とされています。
一見すると和やかに思える場合もありますが、それは互いに気を遣い合っていることでそのように見える可能性があります。できたばかりの組織・チームのため仕方がないですが、相互理解を深めたり、互いに安心して意見をいえる関係性を構築していったりする必要があるでしょう。
混乱期
「混乱期」は、意見・主張の食い違いやすれ違いが生じ、ときには衝突することもある段階です。
混乱期では、相互理解の浅さや、目標・目的の浸透不足などにより、組織・チームのメンバーに食い違い・すれ違いが起こりやすくなります。そのため、互いがコミュニケーションを取りながら相手に対する理解を深めたり、関係構築をしたりして心理的安全性を高めていくことが重要です。
混乱期の組織・チームにおけるコミュニケーションを促進させるには、チームビルディングゲームを活用することが効果的です。以下の記事で、タックマンモデルの各段階に適したチームビルディングゲームを紹介しています。
タックマンモデルの各段階のチームビルディングゲーム25選
統一期
「統一期」は、混乱期を乗り越えて組織・チームが統一されていく段階です。
混乱期を経て組織・チームのメンバー間の相互理解が深まったことで、組織・チームにおける役割を各々が理解し、効率的な連携が少しずつできるようになっていきます。また、組織・チームとしての活動を通じて、各々が組織・チームの目標を理解し、共通認識をもって仕事に取り組めるようにもなります。
機能期
「機能期」は、組織・チームが効率よく機能できる段階です。
機能期の特徴としては、「リーダーが不在でも各々が役割を理解し、最善の行動を取れる」ということが挙げられます。メンバー同士の相互理解、組織・チームの目標・目的に対する理解が十分であれば、リーダーが細かな指示を出さなくても、メンバーの一人ひとりが自律的に行動できるようになります。
そのような状態になると、必然的にメンバーのパフォーマンスが上がり、組織・チームとしての連携が強化されていることで生産性が高まることで、成果・業績が向上することが期待できます。
また、機能期に至ったチームは、メンバーの一人ひとりが組織・チームに属していることにやりがい・働きがいを感じられたり、心理的安全性の高さから精神的な満足感・充足感を感じられたりすることから、離職率の低下にもつながりやすくなります。
このように、タックマンモデルにおける機能期に至ることで、組織・チームが強化され、さまざまなメリットが得られます。
散会期
「散会期」は、目標の達成などにより、組織・チームが解散する段階です。組織・チームの各々が次の目標に向けて動き出します。
タックマンモデルの活用方法
タックマンモデルでは、各段階の組織・チームの状態が具体的に示されているため、活用することで、効果的にチームビルディングをすることができるようになります。
以下では、タックマンモデルの活用方法を紹介します。
組織・チームの状態を見極めるための参考にする
タックマンモデルでは、形成期、混乱期、統一期、機能期のそれぞれの特徴が示されています。
- 形成期:組織・チームが形成されたばかりで緊張している
- 混乱期:メンバーの相互理解が浅いため、関係構築がしにくく意見が衝突しやすい
- 統一期:次第に相互理解が深まり、目標や意識が統一されていく
- 機能期:リーダーが不在でも、メンバーが自律的に行動・連携できる
それらを参考にすることで、組織・チームがどのような状態で、どの段階にあたるのかがわかります。プロジェクトチームのように期間が限定的で、チームができてから日が浅い場合には混乱期にあたる場合もありますが、多くの組織・チームは混乱期と統一期の間にあたると考えられます。
まずは、タックマンモデルを参考にしてチームの状態を見極めることが大切です。
チームビルディングのための改善点をピックアップする
混乱期と統一期の間のどのあたりに位置しているのかを知るには、改善点をピックアップすることが効果的です。たとえば、「相互理解が浅い」、「協力し合っていない」、「別々の目標に向かって行動している」、「互いの思いやりが欠けている」、「コミュニケーションを取る機会が少ない」、「仲が悪い」など、統一期に向かうために必要な改善点をピックアップしていきます。
その後、ピックアップした改善点の程度を見極めていきます。たとえば、「挨拶や業務上のコミュニケーションに問題がないが、協力する姿勢がない」という状態であれば、相互理解やコミュニケーションに関する問題の深刻度は低いが、協力し合うように促す重要度は高いということがわかります。
チームビルディングをはかるには、組織・チームの状態を見極め、分析することが重要です。
改善点を解消するための施策をピックアップする
改善点が明確になれば、具体的な施策を決めていくことができます。たとえば、「協力性が低い」、「コミュニケーションを取る機会が少ない」という改善点が深刻で、それに対する施策を講じる場合は、研修にアクティビティを取り入れたり、懇親会や社内レクリエーションを企画したりして、メンバー同士のコミュニケーションを促進させることが効果的です。
チームビルディングをはかるには、「コミュニケーション」が重要です。相互理解を深めてメンバー同士が互いを理解し、尊重し合うためには、コミュニケーションが不可欠なことが理由です。
コミュニケーションを促進させるには、メンバーのモチベーションや主体性を高めた状態で、お互いのことを知る機会を設けることが大切です。たとえば、懇親会の最初に楽しいアイスブレイク(緊張をほぐすゲームや運動)を取り入れれば、メンバーがリラックスして主体的にコミュニケーションが取りやすくなります。
「あそぶ社員研修」では、アクティビティを通じて主体性を高め、講義・ワークによる学びを深めることができます。また、コミュニケーションを重視した設計のため、チームビルディングにもつながることが特徴です。
チームビルディングにおすすめのアクティビティ17選
以下では、チームビルディングに適したアクティビティ17選を紹介します。
謎パ

謎パは、謎解きとパズルを組み合わせたチームビルディングゲームです。リアルでもオンラインでも実施できます。
みんなで協力して謎のかけらを集めたり、集まった謎を解いたりしながら、ミッションのクリアを目指します。協力して謎を解くことで、チームワークやコミュニケーション能力を向上させることができます。
また、複数のチームに分かれずに参加者全員が1つのチームになるため、参加者全員で一体感や達成感を味わうことができるのもポイントです。
やり方
- 各参加者に問題が配布される
- 他のメンバーとお互いの情報を共有して、謎を解く
- 謎を解き明かしたら次のミッションが発令される
- ミッションを全てクリアすると最終問題に挑戦し、ゴールを目指す
リアル探偵チームビルディング
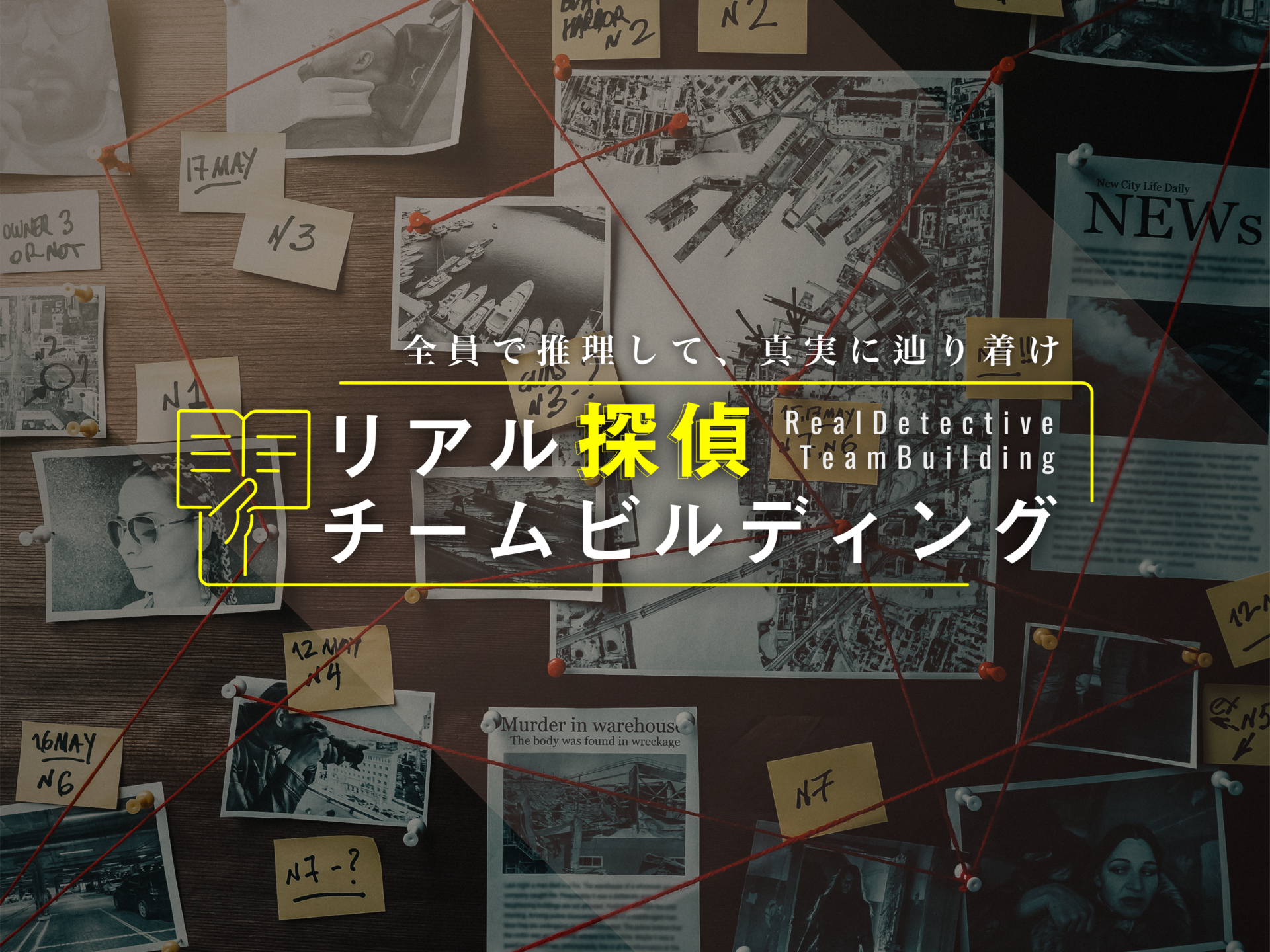
「リアル探偵チームビルディング」は、最大20名の参加者が1チームとなり、全員で力を合わせてミッションクリアを目指すグループワークです。
もともとは人種の壁を取り除くために開発された「ジグソー法」より開発されたビジネスゲームで、目標達成にむけて情報を整理しながら推理する中で、学びが得られる仕組みとなっています。論理的思考や情報分析力・リーダーシップが養われるだけでなく、参加者同士のコミュニケーション促進も期待できます。
リアル探偵チームビルディングの流れ
- 大グループの中で4名~6名人程度の小グループを編成する
- 小グループごとに異なる情報を与える
- 小グループごとに対処法を考える
- 大グループで情報を共有して推理を進める
- 再び小グループに戻り、情報分析や仮説立てを行う
- 大グループで最終的な答えを決める
- 答えの解説を元に小グループで振り返りを行う
リアル探偵チームビルディングは、講義やワークと組み合わせることで、実践的な戦略思考研修としても活用できます。
⇒リアル探偵チームビルディング×ロジカルシンキング研修の資料を受け取る
混乱する捜査会議からの脱出

「混乱する捜査会議からの脱出」はチームで力を合わせてさまざまな証拠品や証言を整理・分析・共有し、事件の真相に辿り着く体験型推理ゲームです。事件を解くには、論理的思考力や情報整理力のほか、役割分担や話し合いが必要になります。
没入感たっぷりの参加者が夢中になれるようなグループワークで、楽しめること間違いなし。ゲームを通じてクリティカル・シンキングを学べるため、ビジネスで活用できるスキルを得られます。
混乱する捜査会議からの脱出の流れ
- 各チームに分かれて着席する
- 推理本番の前にチュートリアルゲームに挑戦する
- チュートリアル後、事件が発生する
- チームに分かれて推理を始める
- 推理の結果を推理報告書に記入する
- 最後に事件の真相について解説
混乱する捜査会議からの脱出は、講義やワークと組み合わせることで、クリティカルシンキング研修としても活用できます。
⇒混乱する捜査会議からの脱出×クリティカルシンキング研修の資料を受け取る
カイジ

「カイジ×チームビルディング~悪魔的社内研修を生き延びろっ… ! ! ~」とは
カイジの世界観に入り込み、カイジのゲームを通してチームビルディングができる、新体験型イベントです。
5名~7名で1チームとなり、各ゲームで「ペリカ」獲得に挑戦します。最終的に獲得したペリカが多いチームの勝利です。ここでしか体験できないユニークな企画内容と圧倒的な世界観の作り込みで、カイジが好きな方はもちろん、全く知らない方でも楽しむことができます。
やり方
- 各チームに分かれて着席する
- ゲームに挑戦し、ペリカ獲得を目指す
- 最終的に獲得したペリカが多いチームの勝利
SDGsビジネスゲーム ワールドリーダーズ

ワールドリーダーズは企業のためにつくられた企業経営を体験できるSDGsビジネスゲームです。
各チームは企業として戦略を立て、労働力や資本を使って利益を競います。
自チームの利益が大きくなるようにゲームを進めていく課程で、チームで戦略を練り、他チームと交渉しながらその場に合った選択をしていかなければなりません。そのため、深いコミュニケーションが取ることができ、チームビルディングにつながります。
やり方
- いくつかのチームに分かれる
- 企業として戦略を立て、労働力や資本で利益を上げる
- 最も多くの利益を上げたチームを優勝とする
⇒ワールドリーダーズで主体性を高め、講義・ワークで実践的に学べる交渉術・ネゴシエーション研修の資料を受け取る
リモ謎
「リモ謎」は、IKUSAが提供する、オンライン上で実施する多人数参加型の謎解きゲームです。Zoomなどのビデオ会議ツールを使えば、1度に最大500人までゲームに参加できます。
進行はプロの演者が行うため、オンラインであっても没入感があり楽しいゲームです。「電脳世界からの脱出」や、「本能寺の変へのタイムスリップ」など、魅力的な物語をベースにしたシミュレーションゲームになっています。チームで協力しなければ謎が解けない仕様となっているため、自然とコミュニケーションの活性化ができます。。
⇒リモ謎で主体性を高め、講義・ワークで実践的に学べるコミュニケーション研修の資料を受け取る
やり方
- オンラインのビデオチャットツールを用意する
- チームで協力をしながら物語にそった謎を時間制限内に解く
- 危機的状況からの脱出を目指す
コンセンサスゲーム
「コンセンサスゲーム」は、意思決定に至るまでの過程を実践形式で学べる研修です。ベーシックなプログラムの「ジャングルサバイバル」、防災知識を習得できる「帰宅困難サバイバル」、ゾンビからの逃亡がテーマの「ゾンビパニック」の3種類から好きなものを選択できます。
準備されたアイデムをどの順序で使用するか、チームで話し合いながら決めていきます。チーム全員が納得した結論に達するには、一人ひとりが意見を出し、議論を重ね、結論に辿り着かなければいけません。
ゲームの実施によって、議論を積み上げたり、意見をまとめあげたりする過程で論理的思考力が養われます。
また、議論を交わすなかで自分とは異なる意見にも耳を傾けることの重要さを学べます。このため、コミュニケーション力や協調性などのスキルも高められるでしょう。
議論をまとめるにはリーダーやファシリテーションの役割が重要です。自然と役割が分担され、チーム内で各々の責務を全うするとはどういったことなのかを学べます。
⇒合意形成研修 コンセンサスゲームで主体性を高め、講義・ワークで実践的に学べる合意形成・アサーティブコミュニケーション研修の資料を受け取る
やり方
- 予期せぬ問題が発生する
- 対処法をまずは個人で考える
- 次にチームで対処法を考える
- 専門家の結論と比べ、自分のチームの対処法の妥当性を確認する
チャンバラ合戦
「チャンバラ合戦」は、戦国時代の合戦に見立て、スポンジでできた刀で敵の命(ボール)を叩くチャンバラ合戦で戦うゲームです。チーム毎に分かれ、戦開始の合図が出たら「オォー!」と雄叫びを上げながら、敵を目がけて突進していきます。もちろん安全性には問題ありませんので、思う存分楽しめるでしょう。
「チャンバラ合戦」では、戦の前に作戦タイムが設けられます。仲間と話し合いながら、敵の意表をつく戦略や陣形を考え、役割分担をしながら連携して勝利を目指します。
⇒チャンバラ合戦で主体性を高め、講義・ワークで実践的に学べるOODA LOOP研修の資料を受け取る
やり方
- 参加者の肩に命(ボール)を付ける
- スポンジの刀を使って相手の命を切り落とす
- 最終的に生き残った人数をチームで競い合う
グレートチーム

「グレートチーム」とはリーダーシップとチームビルディングを学ぶことができるカードゲームです。
4〜5名で1チームとなり、疑似的なプロジェクト運営を行います。プロジェクトを実行し売上を達成するために、メンバーのリソース管理や育成、リーダーとしての決断を繰り返すことで、いろいろなリーダーシップの型を知ることができます。
やり方
- プレイヤーは順番にプロジェクトに割り当てる人を決めていく(アサイン)
- 各プレイヤーはカードに書かれた内容に対して選択を行い再び割り当てを行う(リーダーズチョイス)
- 1~2を繰り返し最終的に売上げが一番高かったチームの勝利
グレートチームは、講義やワークと組み合わせることで、リーダーシップ研修としても活用できます。
ロケットPDCAチャレンジ

「ロケットPDCAチャレンジ」は、PDCAに関する講義・ワークを受けられる研修プログラムです。チーム戦で実施するロケット制作&改善アクティビティと、PDCA講義がセットになっています。
資金を使って部品の購入と発射テストを繰り返し、ゲーム終了時に、最小コストで月まで到達するロケットを作れたチームの勝利です。数千通りあるパターンから成功を導き出す中で、PDCAの過程を体感できます。さらに、アクティビティ実施後にPDCAに関する講義・ワークを受けることで学びが定着しやすく、すぐに業務に活かせる点が特徴です。
ロケットPDCAチャレンジの流れ
- 資金を使って部品を購入し、発射テストを繰り返す
- 数千通りあるパターンから成功を導き出す
- PDCAサイクルの概要を理解する
- 各チームで振り返りを行う
⇒ロケットPDCAチャレンジで主体性を高め、講義・ワークで実践的に学べるPDCA研修の資料を受け取る
陽口ワーク

「陽口ワーク」は、一人がヘッドフォンで耳を隠し、他のメンバーが数分間にわたってその人の褒め言葉をいい続けるグループワークです。本人がいないところでその人の悪口をいう行為を陰口と呼びますが、その逆の褒め言葉を言うというものです。
時間終了後、ヘッドフォンで耳を隠したメンバーが、録音された音声を聞いて陽口の内容を確かめます。自分に向けられた賞賛の言葉を聞くのは恥ずかしいですが、「陽口ワーク」によって、他人が自分のことをよく見てくれていると気づき、承認欲求が満たされます。また、自分では意識していなかった部分が褒められ、新たな長所に気づく可能性もあります。
陽口をいう側にとっても、直接いうのは恥ずかしい内容を伝えられるいい機会になります。他人のいいところを見つける練習にもなるでしょう。
野球のポジション当てゲーム
「野球のポジション当てゲーム」は、限られた情報を組み合わせて、野球大会のメンバーとポジションを当てるゲームです。
このゲームは、各人が持ち合わせる情報を統合させ、知識を補完し、ものごとの全体像を把握する「ジグソーメソッド」に基づいたものです。ジグソーメソッドを実践するには、自分が持つ知識をわかりやすく他人に伝える必要があります。論理的思考力や説明のスキルを養うことができます。
また、反対に他人の発言から学びを得ることも重要です。ゲームを通じて、話を理解して要点をまとめる力が身につくでしょう。
やり方
- メンバーに「情報カード」を配布する
- 5名程度のグループに分かれて議論し結論を導く(メンバーのカードは直接見てはいけない)
- グループごとに発表をする
- 正解発表&フィードバック
NASAゲーム
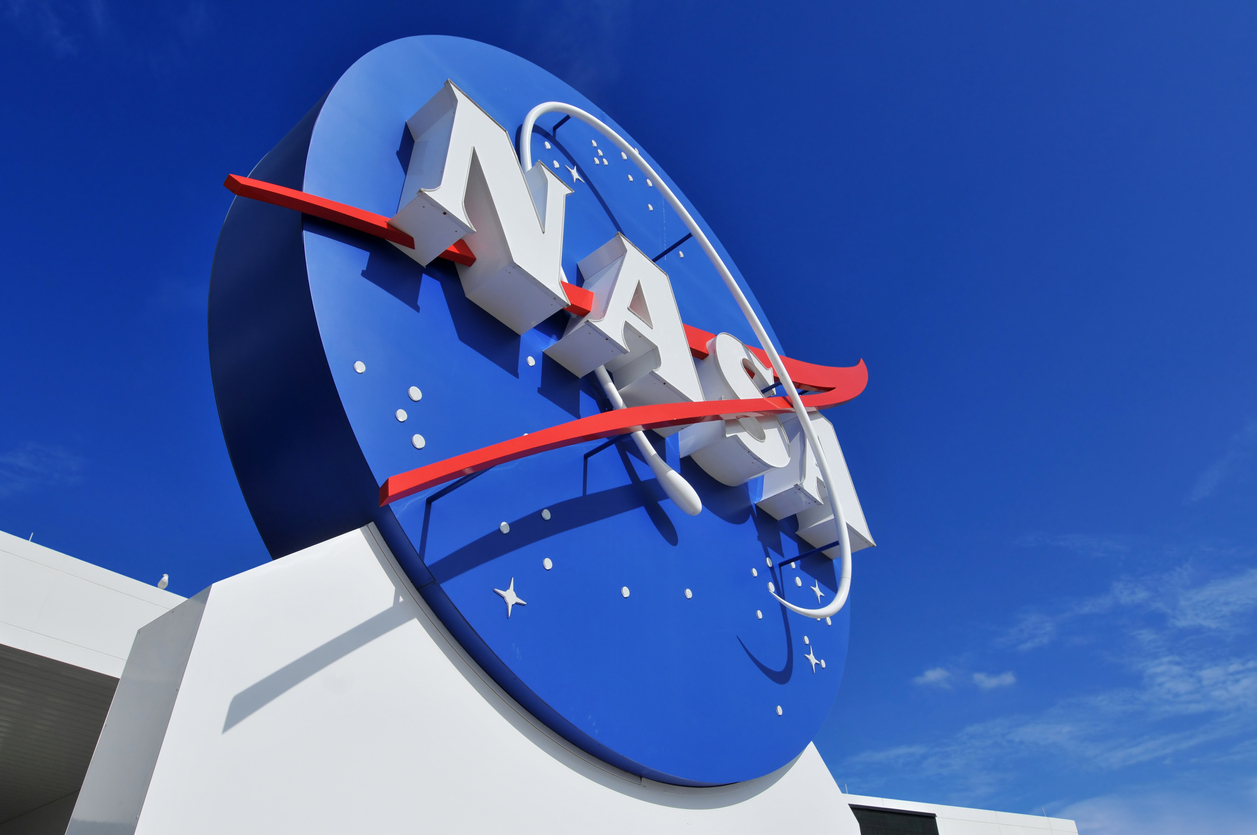
「NASAゲーム」は、15個のアイテムを適切な順序で使用し、不時着した宇宙船から母船まで到着を目指すゲームです。同ゲームは、コンセンサスの過程が学べるゲームで、アイテムの使用順序を決める際は全員一致の決定を下す必要があります。
当然、議論の過程で意見の対立や食い違いが生じるケースはあるでしょう。それでも議論をうまく進行し、ひとつの結論を出さなくてはいけません。
課題クリアのために、リーダーだけではなく一人ひとりが主体的に関わり、議論をまとめていきます。NASAゲームによって、合意形成に至るまでの難しさが把握できるはずです。
同ゲームにはNASAが作成した模範解答も存在します。模範解答に照らし合わせれば、点数や順位付けができますで、ゲームがより盛り上がるでしょう。
やり方
- 「月に不時着した」という状況を把握する
- 個人で15のアイテムの優先度を決める
- グループ内で優先順位を決める
- NASAの模範解答と照らし合わせ、それに近いほど高得点となる
マシュマロチャレンジ
「マシュマロチャレンジ」は、パスタ麺、紐、テープ、マシュマロを使ってタワーを作り、その高さを競うゲームです。同ゲームでは、事前の計画よりも、実際の経験を通して、試行錯誤しながら改善する過程が大切です。理論ばかりに頼らず、実際にやってみて効果的な手法を見出すことが必要です。
また、自立可能なタワーを作るだけでも一苦労なので、高さを追求するためには、組み立て方に関する独創的なアイディアが必要です。
ちなみに、マシュマロチャレンジの世界記録は99cm。斬新なアイディアを出して、1mごえの化け物タワーの建設を目指すとより盛り上がるでしょう。
謎解き脱出ゲーム
「謎解き脱出ゲーム」は、謎を解くためにチーム内で協力する必要があり、高いチームビルディング効果が見込めます。同ゲームの特徴としては、広いスペースを必要とせず、会議室程度の空間があれば実施可能な点です。
脱出ゲームは今人気のコンテンツであり、一般消費者向けにもさまざまな商品が登場しています。従業員のなかには「やってみたい」と感じている人もいる可能性が高く、自然と盛り上がるでしょう。イベントの告知をSNSやブログなどで行えば、集客効果も見込めます。
また、研修以外にも、社員旅行や結婚式の余興などにも利用できる内容です。トレンドを押さえたゲームを行いたい方や、知能をフルに使った大人向けのゲームを探している方は、同ゲームの活用をご検討ください。
⇒謎解き脱出ゲームで主体性を高め、講義・ワークで実践的に学べるコミュニケーション研修の資料を受け取る
やり方
- 制限時間や閉じた空間の中で与えられた謎を解く
- 全ての謎が解けたらゲームクリア
似顔絵当てゲーム

「似顔絵ゲーム」は、その名のとおり、紙とペンを用意して、参加者が似顔絵を描いていくゲームです。似顔絵の対象はみなが知っている社内の有名人物や、世間における著名人を指名すると盛り上がるでしょう。
似顔絵は書く人の性格が表れますので、シンプルながらもやってみると意外におもしろい活動です。たとえば、パーツに着目するのか、表情に注目するのかは十人十色なので、同じ人物の似顔絵を描いているとは思えないケースもあるでしょう。
何よりも手軽に行なえるのが同ゲームの一番のメリットです。ちょっとした隙間時間や息抜きの際にも気兼ねなく楽しめます。
条件プレゼン

「条件プレゼン」は、指定されたキーワードを含めてプレゼンを作成し、みなの前で発表して一番おもしろいものを決めるアクティビティです。魅力的なプレゼンを行うためには、誰も思いつかないトリッキーなストーリーを構築する必要があります。
たとえば、「さる・かに・おにぎり」のワードで「おにぎりをさるに取られたかにが○○○」と話をしても、おもしろくありません。独創性やアイディア力を発揮した、奇想天外な展開が求められます。
また、伝え方や表現にも気を配る必要があります。聞く人の興味を引くにはどのような伝え方をすればいいか、頭の中でイメージを沸かせるにはどのような言葉を使えばいいのかといった点を考えるのが重要です。
難易度が低いゲームではありませんが、大切なのは楽しむことです。他のメンバーが発表する際も、積極的に笑い声をあげ、場を盛り上げるよう配慮しましょう。
まとめ

タックマンモデルを活用することで、現状の組織・チームの状態を分析し、チームビルディングに関する効果的な施策を講じることができるようになります。
目次

ビジネスゲーム研修.comでは、研修のお役立ち情報や、体験型研修の事例をご紹介しています。オンライン研修やチームビルディング研修をお探しの方は、ビジネスゲーム研修.comにお任せください。