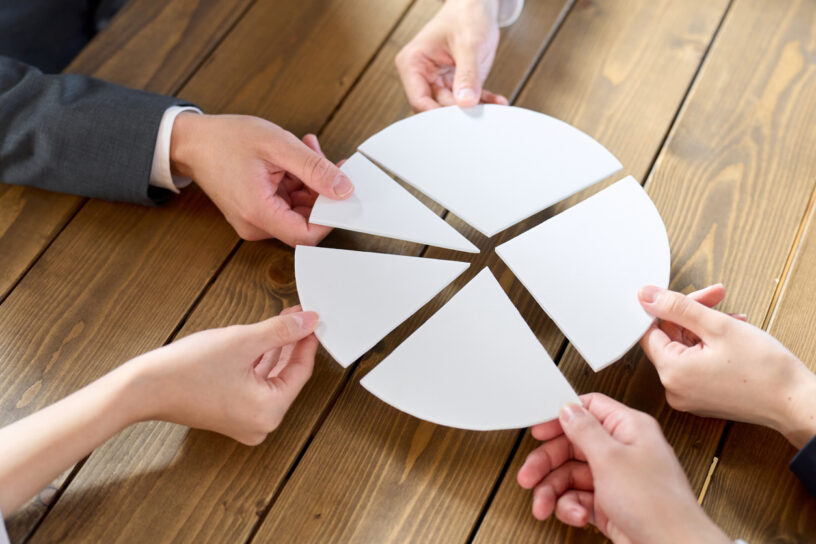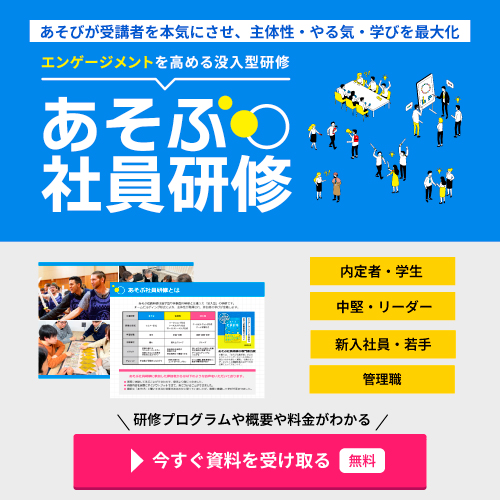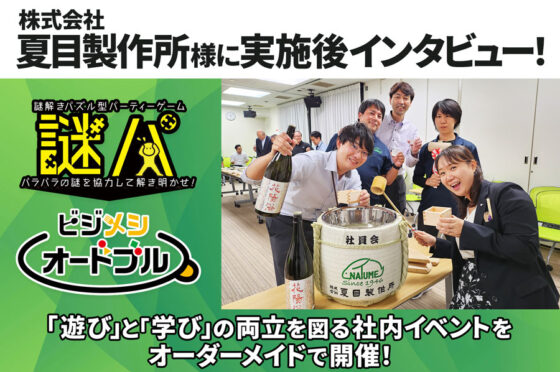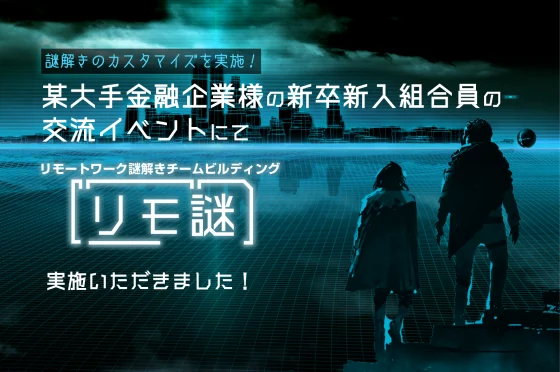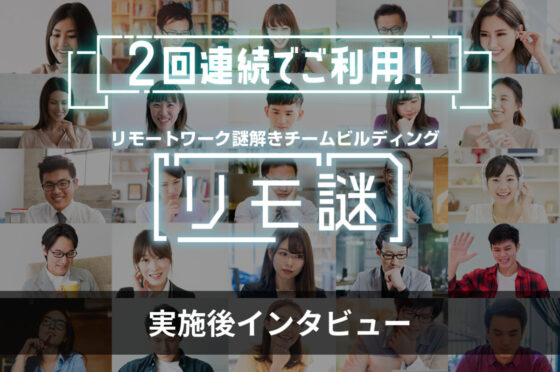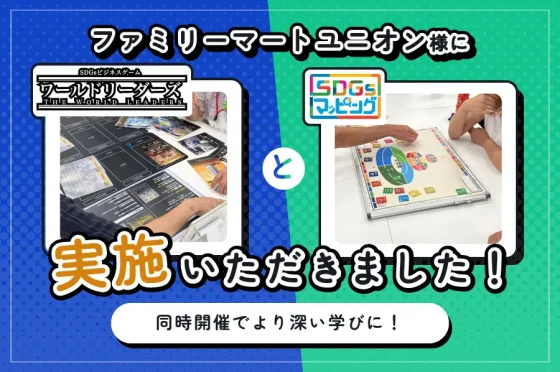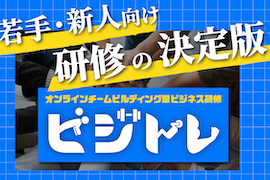- ビジネスゲーム
- フレームワーク
- チームビルディング
チームビルディングにサバイバルゲームが役立つ理由とは?概要・ルールも解説

目次
サバイバルゲーム(サバゲー)は、メンバーが同じ目標に向かって取り組んだり、目標達成のために細かなコミュニケーションが必要なことから、社員同士のチームビルディングに効果的で、企業でも取り入れられています。
サバイバルゲームというと初心者にはハードルが高いように捉われがちですが、初めてでも楽しく取り組めるうえ、仕事をする上で役立つ実践的スキルを身に付けるためにも有効です。
本記事では、サバイバルゲームの概要やルール・試合形式、チームビルディングに役立つ理由と注意点、さらにおすすめのサバイバルゲームのプログラムをお伝えします。
アクティビティ・振り返り・専門講師が行う講義をブリッジし、受講者の主体性・学びを高める「あそぶ社員研修」とは?
⇒無料で資料を受け取る
研修にビジネスゲームを取り入れてチームビルディング。「ビジネスゲーム研修 総合資料」を無料で配布中
⇒無料で資料を受け取る
そもそもサバイバルゲームとは?

サバイバルゲームとは、銃(エアソフトガン)で撃ち合って生き残りをかけて戦うゲームで、日本では1980年代に広まったといわれています。
チーム戦で行うことが多く、専用の銃を用いて、森や公園・サバイバルゲーム専用の競技場でプレイします。
敵に撃たれたプレイヤーは「ヒット!」と言って退場になるルールですが、味方チームが撃った球や自分で撃った球が跳ね返って当たった場合もアウトになります。チームメンバーで協力して敵を追い詰め、自分や他のメンバーが生き延び、チームが勝利できるよう作戦を立てながら行動する必要があります。
研修の企画にお困りですか? IKUSAの研修なら楽しくチームビルディングができます!
⇒IKUSAの研修資料を見てみたい
サバイバルゲームがチームビルディングに役立つ理由

サバイバルゲームは楽しいゲームでもありますが、勝つためには作戦や役割分担が重要なアクティビティでもあります。企業の研修やイベントで取り入れるならば、チームビルディングや社員同士のコミュニケーションの活性化を図るとよいでしょう。
1.メンバー間で同じ目標に向かって取り組める
チーム戦でのサバイバルゲームでは、攻守を分担したり、地形を上手く活用したりと、作戦や役割分担をして個々が主体的に動く必要があります。互いにコミュニケーションをとり、相手の立場に立って積極的に声掛けをするなど、協力して作戦を遂行することで、一体感を味わうことができます。
2.メンバー間の相互理解に繋がる
部署やチーム、年齢などが違うメンバーとチームになった場合、お互いの考え方やアイデア、体力や運動神経などを知るきっかけになるでしょう。それまで関わりがなかった人や、知ってはいたけれど関係性が深くなかった人とも相互理解をするきっかけとなり、よく職場づくりに役立つでしょう。
3.スポーツ経験や体力に関係なく楽しめる
サバイバルゲームの経験が豊富という人はあまり多くなく、シンプルなルールなので、年齢や性別に関係なく全員が楽しめます。スポーツが苦手、という人がいるかもしれませんが、多くの場合はうまく役割分担をして取り組め、体を動かすことによる気分転換効果も期待できます。
4.達成感、連帯感を味わえる
普段の業務だけではなかなか味わえない、達成感、連帯感が感じられるのがチーム戦でのゲームのメリットです。非日常的なシチュエーションでのゲーム体験を共有することで、仲間意識を育むにもおすすめです。
5.協調性、主体性が養える
チームで作戦に沿って行動する場合、自分勝手な態度をとるメンバーがいるとチームとしての勝利は難しいでしょう。足並みを揃え、協力して取り組む必要がある点で、仕事にも有益な協調性を養えるでしょう。また、作戦によって個々が行動をする際は、指示待ちではなく自らの行動で自分やメンバーを守り、攻撃する必要があります。その点でも、主体的に考えて行動する実践的スキルを養うことができます。
サバイバルゲームの形式

サバイバルゲームの戦い方はいくつもあります。ここでは、5パターンの戦い方を見てみましょう。
1.ダメージ戦
被弾した場所によって、行動が制限される試合となっています。球がヒットした箇所によって、行動が制限されます。たとえば、このような形です。
例1:腕に被弾した場合
- 1回目のヒット:当たった方の腕が使えなくなる(銃の操作や操縦もしてはいけない)
- 2回目のヒット:両腕が使えなくなる
- 3回目のヒット:退場
例2:足に被弾した場合
- 1回目のヒット:走ったりしゃがんだりできなくなる
- 2回目のヒット:一歩も動けなくなる
- 3回目のヒット:退場
例3:首から上と胴体
- 1発当たったら退場
球が当たった場合は「腕、ヒット!」という感じで「当たった箇所+ヒット」と発言します。なお自分の体をうまく使えば、敵チームに撃たれたとしても生き残れる確率が上がります。
仮に首から上や胴体を撃たれそうになった場合であれば、腕に当たるよう防御すれば一発で退場しなくて済みます。うまく防御しながら自分を守り抜いてみてください。
2.殲滅(せんめつ)戦
いずれかのチームが全滅するまで戦います。敵チームを全滅させたチームの勝利となりますが、制限時間内に全滅しなかった場合は、試合が終わった時点でプレイヤーが多く残っているチームの勝ちです。
殲滅戦では、攻めることばかりに集中していては勝てません。気づかないうちに背後から回られたり、複数の敵メンバーに囲まれたりするおそれがあるため、守備面でもしっかりと作戦を立てておくことが必要です。
3.拠点制圧戦
お互いに敵チームの拠点を取り合うゲームで、全ての拠点を制圧したチームの勝利となります。ルールは以下のとおりです。
- 各チーム拠点を5ヵ所設ける
- 敵チームの拠点に入ったら、味方チームのフラッグを立てる
- どちらかのチームが、5分の3以上制圧したらゲーム終了
「どのような順番で拠点を制圧していくか?」「味方チームの拠点をどのように守るか?」が大切になってきます。順序良く敵チームの拠点を制圧できるかが勝負のカギです。
4.籠城戦(片陣戦)
攻撃側と防御側に分かれて、制限時間内に敵チームに立てられたフラッグをとる(守る)ルールになっています。攻撃側は敵チームが撃ってくる球をよけながらフラッグをとり、防御側はフラッグをとられないよう、攻撃側に向かって撃ちながら守ります。
制限時間内にすべてのフラッグをとれれば「攻撃側」、とられなければ「防御側」のポイントです。攻守を交替しながら何回戦か行い、最終的にポイントが多かったチームの勝利となります。拠点制圧戦とは違って、攻めor守りに徹することができるため、プレイしやすいかもしれません。
5.バトルロワイアル
最後の一人になるまで撃ち合うゲームで、最後の一人として残った人の勝利です。全参加者が敵なので、誰からも撃たれないようにする必要があります。
勝利のコツは、誰にも見られない場所に隠れること。チームとして勝利を目指すのであれば、最後まで生き残らせる人を決め、その他のメンバーが攻撃役となるなど、作戦を立てておくことが大切です。全員が隠れるだけでは撃ち合いが起きず、ゲームが進行しないので、積極的に攻撃をしかけるようにルールを設けると良いでしょう。
サバイバルゲームをするときの注意点

サバイバルゲームをするときには、いくつかの注意点があります。こちらも押さえておきましょう。
自分勝手な行動をしない
団体戦の場合は、自分勝手な行動をしないようにしましょう。それがチームの敗北要因につながるおそれがあるからです。
- 他のメンバーが勝手に動いたから、チームワークが乱れた
- フォーメーションが崩れて、敵チームに攻め込まれた
- 勝手に動いているメンバーを注意したときの声が聞こえてしまった
上記のことがきっかけとなり、敗北してしまうこともあります。自分だけ目立とうとせずに、チームで和を乱さずに行動することを心がけましょう。
チームの組み方を考える
サバイバルゲームを楽しむためには、チームごとの実力が拮抗している方がおすすめです。「サバイバルゲームの経験者のみで固めない」「さまざまな年齢のメンバーを混ぜる」など、対策方法はいろいろあるので、バランスのよいチーム変遷を考えましょう。
ルールの説明をしっかりとしておく
対戦形式がいろいろとあるため、ルールの説明は事前にしっかりと行いましょう。シミュレーションを交えて具体的に解説すれば、初心者もよく理解して取り組みやすくなります。
不正をさせない
たとえば「ヒットしたのに撃たれていないと言う」など不正をさせないことも大切です。不正が起こると、参加者の士気が落ちることになりかねないので注意しましょう。
審査員やスタッフなどを所々に配置すれば、人の視線があるので抑止力につながるかもしれません。サバイバルゲームでは「当たった・当たっていない」の口かけ論が起こることもあるため、スムーズにゲームが進む体制を整えておきましょう。
ゲーム終了後に交流する時間を作る
ゲーム後は、チームメンバーでの交流する時間を作りましょう。これはコミュニケーションを活発化させるだけではなく、迷惑をかけてしまったプレイヤーに謝る時間でもあります。この時間をとったことで参加者同士のコミュニケーションが活発化して、職場でも同僚同士で話しやすくなるかもしれません。
職場によっては、今まで交流がなかった人と急に一緒に仕事をすることになる場合もあります。そういった状況になってもいいよう、交流する時間も大切にしましょう。
研修要素をプラスしたサバイバルゲーム「サバ研」もおすすめ

IKUSAでも「サバ研」というサービスを提供しています。これは「サバイバルゲーム」と「人材研修」を掛け合わせたプログラムで、サバイバルゲームをしながらチームビルディングを磨ける研修です。

特徴は「見る→分かる→動く→決める」を高速で回すサイクルである「OODA LOOP」の要素を取り入れていること。
アメリカの空軍で活動していた「ジョン・ボイド大佐」が作った「勝つための」フレームワークだといわれており、OODA LOOPをスピーディーに回し、状況に迅速に対応しながらチームとしての目的を達成する実践的な考え方が身に付きます。
さらにリーダーシップも身につくので、管理者向けの研修にも適しています。ゲームを通じながら、リーダーとして必要なスキルを学べます。
その他にも「サバ研」には、以下のような特徴があります。
1.防護グッズのレンタルがある
迷彩服やゴーグル・エアガンなどのレンタルを用意してるので、自分でサバイバルゲームグッズを購入していただく必要はありません。球が発射されない「レーザー銃」の取り扱いもあるので、球がヒットしたときの痛みを軽減したい人にもピッタリです。
さらに対人賠償や治療費保障の保険にも加入しているので、サバイバルゲーム中にケガをしてしまったときも、条件に該当すれば治療費用などが保障されます。
2.初心者講習がある
サバイバルゲーム開始前には、初心者講習を設けています。銃の取り扱い方法や撃ち方など、わかりやすく説明しますので、銃の操作をしたことがない人も安心してサバイバルゲームに取り組めます。
3.専門スタッフが指導
当たっても痛くないレーザー銃の利用もできる他、不注意による怪我などがないように専門のスタッフが万全の注意を払います。銃の取り扱いから危険行為など安全にサバイバルゲームを行う為に、初心者講習を実施致します。
なお、サバ研は開始から終了まで3~7時間の間でスケジュールを組めます。1日がかりで実施したい企業だけではなく、極力短時間で済ませたい企業にもおすすめです。
運動不足の解消も期待できるので、普段運動をしない人が多い場合も、ぜひ検討してみてください。
まとめ

サバイバルゲームは、ゲームではあるものの団体競技であるため、チームビルディングを磨くのに適しています。記事中で紹介したサバ研の場合、試合前にルールを詳しく説明するので初心者も気軽に楽しめるはずです。
サバイバルゲーム専用の競技場も全国各地にあるので、ぜひ活用してみてください。
「あそぶ社員研修」は、受講者全員が没入して取り組むアクティビティ・振り返り・講義をブリッジすることで学びを最大化させ、翌日から業務で活かせる知識・スキルが身につく講義・アクティビティ一体型の研修プログラムです。
アクティビティが受講者の主体性を高めてコミュニケーションを促進させ、スキルアップやチームビルディングをはかれます。
研修やチームビルディングイベントの企画にお悩みの方必見!「ビジネスゲーム研修 総合資料」では、謎解き、推理ゲーム、サバイバルゲームなどを活用したユニークな研修を事例とともにご紹介しています。
目次

ビジネスゲーム研修.comでは、研修のお役立ち情報や、体験型研修の事例をご紹介しています。オンライン研修やチームビルディング研修をお探しの方は、ビジネスゲーム研修.comにお任せください。