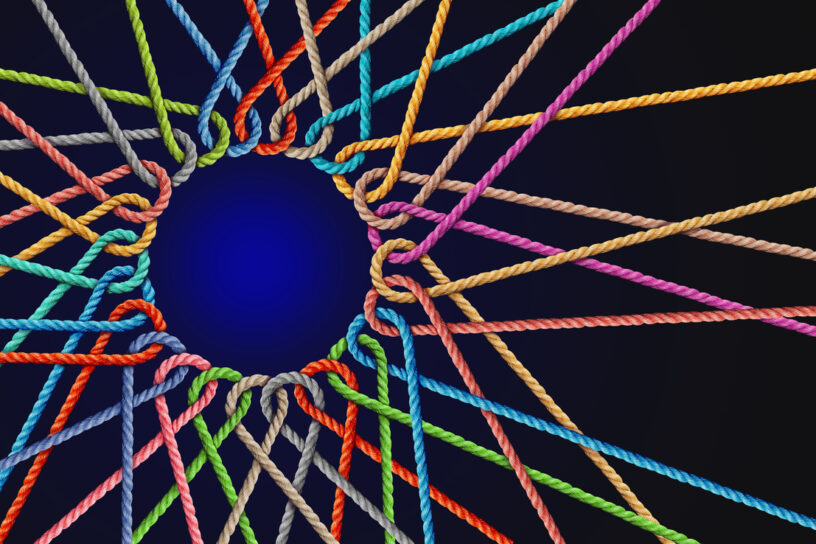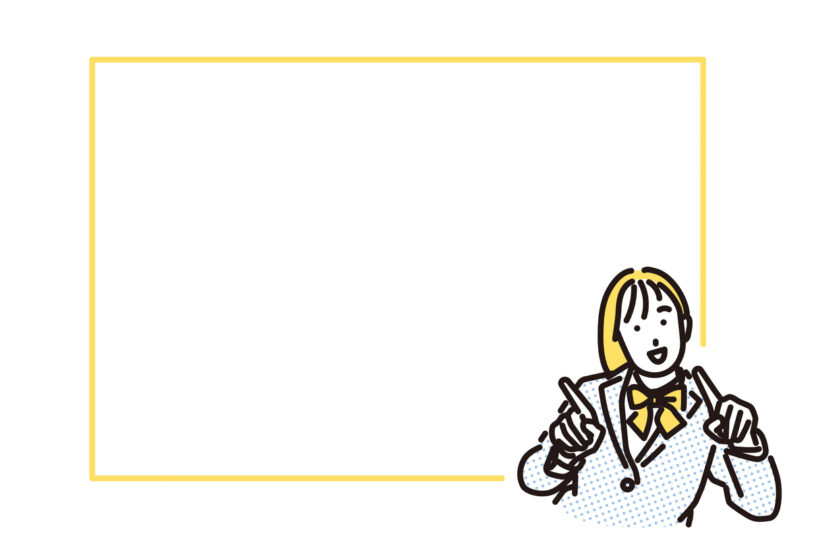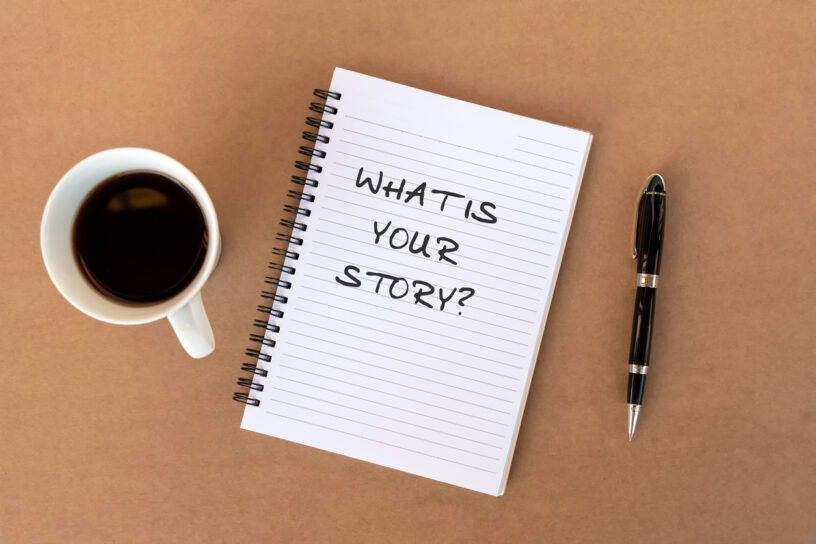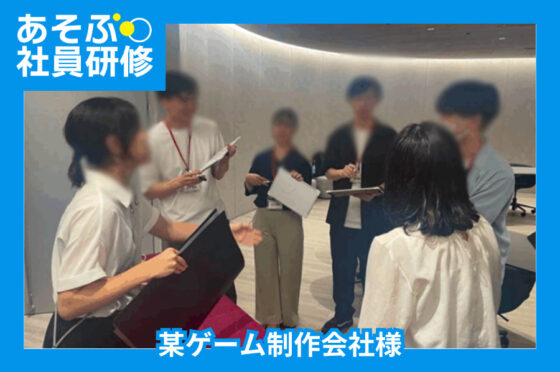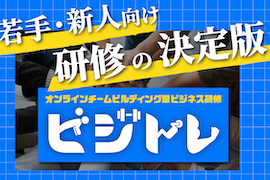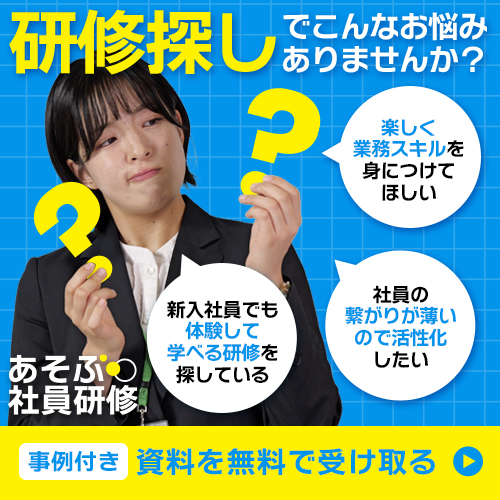- フレームワーク
- フレームワーク
ブレインストーミング(ブレスト)の方法とルールを解説


目次
方針を立てる際や、施策について検討する際など、ビジネスシーンで「たくさんのアイデアを出す」ということが求められる場合、ブレインストーミングを行うことが効果的です。また、相互理解を深めたり、共感を得られたりすることで、チームビルディングにつなげることもできます。
本記事では、ブレインストーミング(ブレスト)の概要、実施する目的、前提となるルール(5原則)、実施方法、関連するフレームワークを紹介します。
ブレインストーミングとは

ブレインストーミングとは、特定の問題・課題に関して、独創的な大きなアイデアを生み出すためのフレームワークです。
アメリカの心理学者「アレックス・オズボーン」によって考案された手法であり、1948年の著書「Your Creative Power」を通じて提唱されたといわれています。ブレインストーミングは、略して「ブレスト」とも呼ばれます。
参考:ブレインストーミングの効用―臨床社会学や文章作成法との関連で―(PDF)
ブレインストーミングは、グループディスカッションの形式で行われることが多いですが、1人で黙々とアイデアを書き出していく形で実行することもできます。
ブレインストーミングを実施する目的
文部科学省が公開している「指導方法の在り方」によると、ブレインストーミングでは、「創造性を促進させること」、「多くのアイデアを短時間で生み出すこと」の2点がメリットとして挙げられています。
また、文部科学省の「イノベーション対話ツール ワークショップで用いる基本手法解説書」によると、ブレインストーミングの目的として、「思考の発散」、「相互理解」、「共感」が記載されています。
参考:イノベーション対話ツール ワークショップで用いる基本手法解説書|文部科学省(PDF)
上記から、ブレインストーミングを実施する目的は、以下の2点に大きく分けられるといえます。
- 創造的なアイデアを生みだすこと
- 相互理解や共感によるチームビルディング
ブレインストーミングは、創造的なアイデアを生むために会議・ミーティングで行われる一方で、社内レクリエーションや研修などを通じてのチームビルディングを目的としても活用されています。
ブレインストーミングの前提となるルール(4原則)

- 批判してはいけない(批判厳禁)
- 自由奔放にアイデアを出す(自由奔放)
- 質より量を重視する(質より量)
- アイデアの結合・改善をはかる(結合改善)
上記が、ブレインストーミングを行う際の基本的なルール(4原則)です。
自由奔放に、アイデアを思いつく限り出したうえで、他者のアイデアを批判せずに、アイデアをまとめたり発展させたりすることも思考することが、ブレインストーミングを行う際には重要となります。
ブレインストーミングの実施方法

ここからは、グループ(複数人)でブレインストーミングを行う際の方法(進め方)を紹介します。
Step1:目的・課題を決める
ブレインストーミングは「独創的なアイデアを生み出すための手段」ではありますが、「たくさんのアイデア出すこと」や、「相互理解や共感を促すこと」なども実施する目的になり得ます。ブレインストーミングを実施する際には、まずは目的を明確にすることが重要です。
また、ブレインストーミングを実施することで解決したい課題を挙げることも大切です。そのうえで、課題解決につながる設問を用意します。たとえば、「より良いチームにするためにチームの問題点を挙げる」という設問を用意することで、課題に対する問題点について参加者が共通認識を持つことにつながります。
Step2:ファシリテーター(進行役)を決める
ブレインストーミングは、以下のようなプロセスで行われます。
- ルール・設問などの説明
- アイデア出し
- アイデアのまとめ・改善
ファシリテーターを決めておくことで、時間管理・進行管理を行ったり、ルール違反を指摘したりして、効果的かつ円滑な進行を促せます。
Step3:全員でアイデアを出し尽くす
ブレインストーミングでは、「質より量」を重視して、どんどんアイデアを出すことが重要です。ただし、考えてもアイデアが出なくなってからも続ける必要はありません。20~30分程度の制限時間を決めておき、アイデアが出なくなったら終了時間を待たずに次の段階に進めることも大切です。
アイデアを書く方法
- 【対面・オンライン】スプレッドシートなどの共有可能なアプリケーションを活用する
- 【対面】付箋(ポストイットなど)にアイデアを書き出す
ブレインストーミングを行う際に、アイデアを書く方法としては上記の2つが挙げられます。対面形式でブレインストーミングを行う際は、貼る場所を簡単にかえられる付箋を活用する方法がおすすめです。
Step4:アイデアをグルーピングする(KJ法)
アイデアが出尽くしたら、近しいアイデアをまとめる作業(グルーピング)を行います。そのようにすることで、それぞれのアイデアがグループごとに可視化され、アイデアの改善・発展をはかることができます。
アイデアのグループ化を行うことで、ブレインストーミングのルール(4原則)の1つである「アイデアの結合・改善をはかる(結合改善)」がしやすくなります。ブレインストーミングでは、アイデアを否定せずに、すべてのアイデアを活かすことが大切です。アイデアを出し尽くして終わるのではなく、グループ化を行うことがおすすめです。
具体的なグルーピング方法については、以下で「KJ法」、「セブンクロス法」を紹介します。
アイデアをグルーピングするフレームワーク「KJ法」
KJ法は、グループ分けをしてアイデアを整理するフレームワークです。KJ法を活用することで、ブレインストーミングで挙げたアイデアを大グループ・小グループにグルーピングし、整理することができます。
- 小グループ:まず近しいアイデアを小グループに分けます。
- 大グループ:関連性の高い小グループをまとめて大グループをつくります。
KJ法を活用することで、量を重視して挙げたアイデアを整理し、より具体的に可視化することができます。そのようにすることで、アイデアを統合して新たなアイデアを生み出したり、アイデアを改善したりする次のステップにつなげることができます。
アイデアを整理して優先順位をつけるフレームワーク「セブンクロス法」
セブンクロス法とは、7×7のマスを作成し、行は優先順位、列はグループで記載することで、アイデアのグループごとの優先順位を可視化することができるフレームワークです。
ポイントは、グループごとのアイデアの優先順位に加え、グループのなかの優先度についても検討することです。7×7のマスを埋めていくことで、「より優先度が高いグループのなかで最も優先順位の高いアイデア」がわかります。また、各グループのなかで優先順位の高いアイデアがわかることで、重要なアイデアが可視化されます。
近しいアイデアをまとめてグループをつくる方法KJ法と同じで、セブンクロス法ではアイデアの優先順位を検討します。セブンクロス法では7つのグループを作成するのが基本的な方法となりますが、グループやアイデアが8つ以上ある場合にも、「優先順位をつけて明確に記載する」というルールに則っていれば問題ないといえます。
Step5:アイデアの結合・改善について検討する
アイデアのグループ化を行ったら、「アイデアの結合・改善」について検討します。アイデアを組み合わせたり、発展形を考えたりすることで、より良いアイデアが生み出されることがあります。
ブレインストーミングを行う際には、「より良いアイデアを生み出す」まで行うことがおすすめです。その際にも、否定的な意見を出す(批判をする)のではなく、肯定的にアイデアを出していくことが重要です。
ブレインストーミングと関連するフレームワーク
以下では、アイデア出しに関するその他のフレームワークを紹介します。
マインドマップ
マインドマップとは、頭のなかにあるイメージを可視化するためのフレームワークです。
マインドマップでは、まずは主題を明確にし、それに関連するものをグループごとに書き出していきます。マインドマップを行う際には「イメージの可視化」が重要であるため、イラストを描いたり、線を滑らかな曲線だけにしたりすることがポイントとなります。
マインドマップでは、思いつく限り、イメージできるものをすべて書き出すため、アイデアのヒントを網羅的に書き出すことができます。
また、自分の頭のなかにあるものが可視化されることで自己理解が深まります。そのため、グループワークとして実施し、マインドマップを共有し合うことで、相互理解を深めることもできます。
マインドマップについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。
関連記事:マインドマップとは?ビジネスで活用するメリット・作り方を紹介
その他、考える力を育てるゲーム5選
ロケットPDCAチャレンジ

ロケットPDCAチャレンジは、ロケット発射の成功を目指す体験型ゲームです。ロケットを制作する過程で、計画(Plan)から実行(Do)、振り返り(Check)、改善(Action)までのサイクルを繰り返し体感し、PDCAの重要性を学びます。チームビルディングにも効果的です。
謎解き脱出ゲーム

謎解き脱出ゲームは、制限時間内に仲間と協力して謎を解き、ある空間から脱出する体験型ゲームです。参加者同士が自然に声を掛け合い、情報共有や役割分担を行うことで、コミュニケーション力とチームワークを高められます。研修や懇親会のアイスブレイクにも最適です。
ワールドリーダーズ

ワールドリーダーズは、与えられた労働力や資本を使ってさまざまなアクションを起こし、利益を拡大させていくビジネスゲームです。他グループとの駆け引きや同盟、戦略的な意思決定を通じて、交渉力・戦略的思考力を育成します。
混乱する捜査会議からの脱出

混乱する捜査会議からの脱出は、推理ゲームを通じてクリティカルシンキングを学ぶことができるビジネスゲームです。さまざまな証拠品や証言を整理・分析・共有し、論理展開や仮説思考を駆使することでクリティカルシンキングを実践的に学べます。
グレートチーム

グレートチームは、リーダーシップとチームビルディングを学ぶことができるカードゲームです。
4〜5名で1チームとなり、疑似的なプロジェクト運営を行います。プロジェクトを実行し売上を達成するために、メンバーのリソース管理や育成、リーダーとしての決断を繰り返すことで、いろいろなリーダーシップの型を知ることができます。
まとめ
ブレインストーミングを活用することで、複数人で多くのアイデアを出し尽くすことができます。また、KJ法やセブンクロス法などを活用し、アイデアをグルーピングすることで、さらに良いアイデアについて検討することもできます。
会議や研修でブレインストーミングを活用し、自由な発想でアイデアを集め、課題解決を促しましょう。
目次

ビジネスゲーム研修.comでは、研修のお役立ち情報や、体験型研修の事例をご紹介しています。オンライン研修やチームビルディング研修をお探しの方は、ビジネスゲーム研修.comにお任せください。