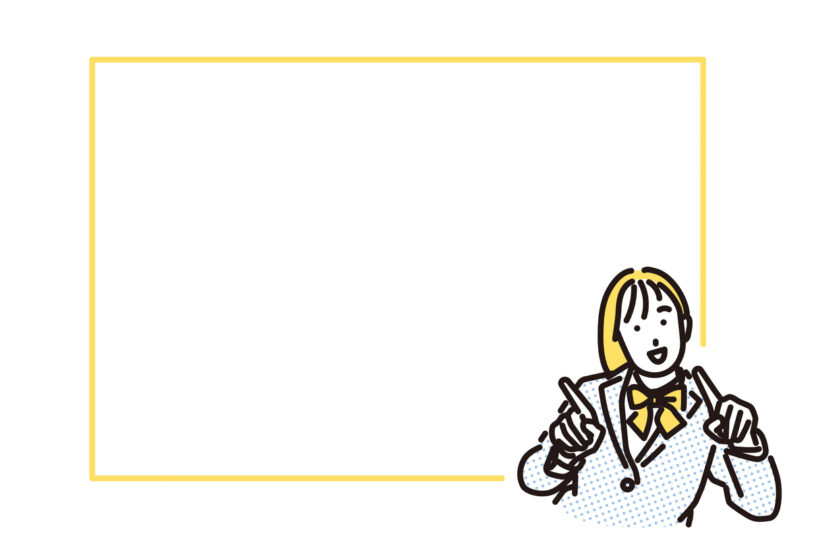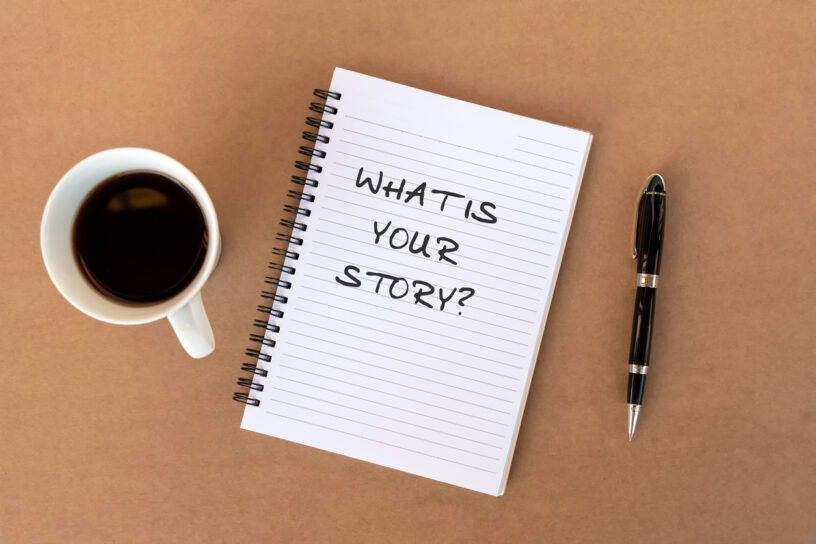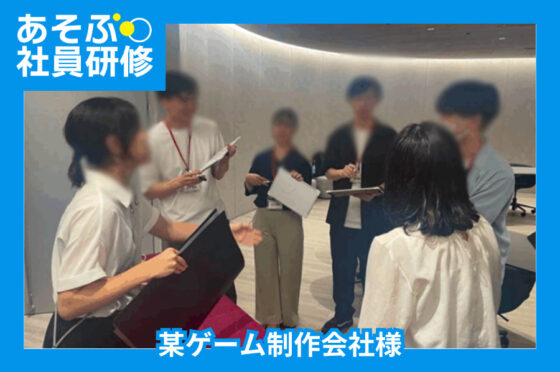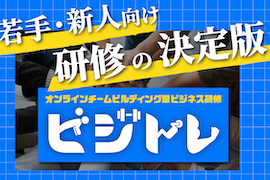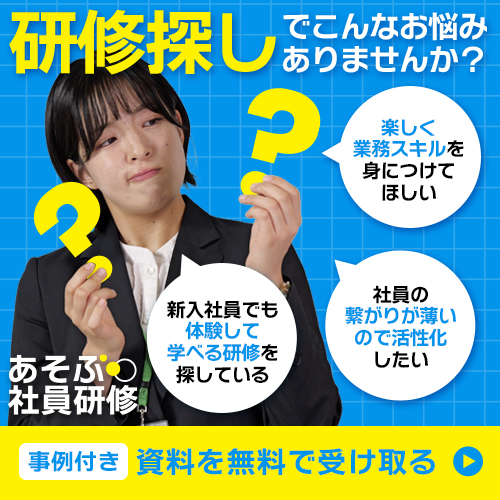- チームビルディング
- チームビルディング
チームビルディングに関する本(書籍)15選
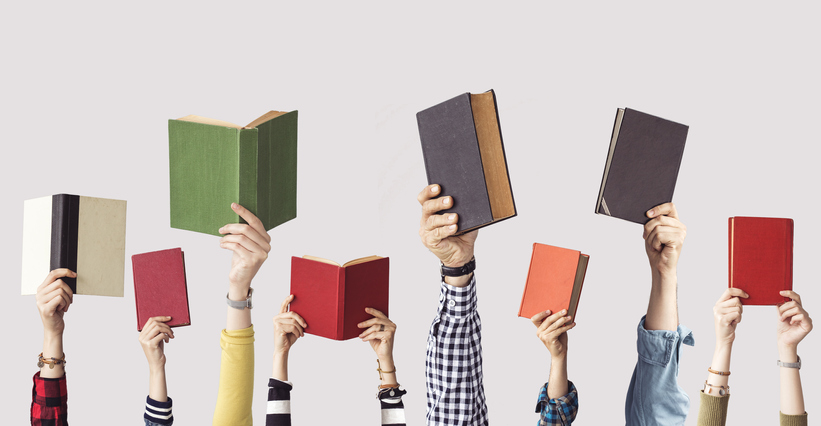

目次
チームビルディングは、互いが深く理解し合い、主体的に目標に向かって連携できる組織づくりです。
本記事では、チームビルディングに関連する本(書籍)15冊を紹介します。
チームビルディングとは

チームビルディングとは、チームを構成するメンバー同士が深く理解し合い、目標に向かって主体的に連携できる組織づくりをするための取り組み全般を指します。チームビルディングに成功した組織は、リーダーに頼らずとも、目標に向かってメンバーが主体的に行動できることが特徴です。
- 相互理解
- 主体性・モチベーション
- 協力姿勢・思いやり
- 帰属意識・エンゲージメント
チームビルディングを成功させるには、上記の4項目が重要です。コミュニケーションを促進させ、チームづくりを進めていきましょう。
チームビルディングの目的・効果
企業がチームビルディングに取り組む理由は、ビジネスである以上、「業績の向上」が主となりますが、それに紐づく「離職率の低下」、「生産性の向上」などが目的として挙げられます。
チームビルディングに取り組むことでチームの人間関係が改善され、連携強化、心理的安全性の向上などにつながることで、より成果を出せるチームに近づいていきます。
チームビルディングに関する本(書籍)15選

ここからは、チームビルディングに関する本(書籍)15冊を紹介します。
Team Geek(著者:ブライアン・W・フィッツパトリック、ベン・コリンス・サスマン)
チームで仕事やプロジェクトを進める際には、一人ひとりの能力や技術が優れていても、各々がただ作業を行うだけではチームとしての機能を最大限に発揮できません。
本書では、Googleでエンジニアを経てプロジェクトリーダーとなった著者が、「エンジニアが他人とうまくやる」コツについて書いています。「チームを作る三本柱」「チーム文化のつくり方」「有害な人への対処法」といった、エンジニアがチームで仕事をするうえで求められる社会性について、事例と共に学ぶことが可能です。
エンジニア経験を元に書かれた一冊ではありますが、チームとして成功をおさめるための方法や考え方はチームビルディングにおけるさまざまな場面で応用できます。チームビルディングを学びたい方にとっては読みやすい一冊といえるでしょう。
チームが機能するとはどういうことか–「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ–(著者:エイミー・C・エドモンドソン)
「チーム」とは、かつては「空間と時間を共有する固定的な集団」というイメージがありました。しかし、さまざまな技術が発展し、人々の生活様式や働き方が多様化しつつある現代社会では、チームは「目的達成とともに解散する流動的な集団」へと役割を変えつつあります。
本書には、時代と共に変化するチームを機能させるために必要なものを、著者の「チーミング」と呼ばれる概念をもとに、新時代のチーム作りについて書かれています。
なお、著者であるエイミー・C・エドモンドソン氏は、ハーバード・ビジネススクールの教授としてリーダーシップと経営論を担当しています。発表した論文は60を超え、学術誌や経営雑誌で取り上げられたこともある経歴を持つことからも、専門的な視点からのチームビルディングを学びたい方にはおすすめの一冊です。
なぜ人と組織は変われないのか–ハーバード流 自己変革の理論と実践–(著者:ロバート・キーガン)
問題や課題を抱えたとき、人は変わる必要性を認識していても行動までに繋がらないといわれています。本書では、オリジナルの「免疫マップ」を活用して、人々の「変わりたくても変われない」という深層心理から自己防衛のメカニズムを解き明かし、行動を起こせるような自己改革・組織改革を目指します。
組織のリーダーやメンバー、企業の経営陣、プロジェクトチームなど、チームビルディングが求められる状況に役立つ一冊です。「免疫マップ」を実践し、さらなる組織改革に向けた行動に繋げましょう。
中小企業の退職者撲滅法!! 不機嫌な職場を上機嫌な職場に変える! 楽習チームビルディング(著者:藤咲徳朗)
本書では、一定数の企業には、メンバー同士が不信感にあふれ、助け合うことや教え合うことができない状況である「不機嫌病」が蔓延していると述べています。その不機嫌病の処方箋として著者が本書で掲げているのが「楽習チームビルティング」と呼ばれるアクティビティです。
本書には、著者が実際に企業で使っている55個の楽習チームビルディングのコツやカリキュラムを満載しています。楽習チームビルディングの実施により、「新卒採用者が1年間で4割以上退職していた企業の退職者が0になった」「業績が増収増益になった」という事例もあり、職場風土の改善にも期待ができます。
ぜひ楽習チームビルディングを実践して、より活気のあるチーム作りに育んでみてはいかがでしょうか。
C3チームビルディング–結果をもたらす「コーチング」と「リーダーの思考改革」–(著者:小島圭市)
本書では、アメリカMLB(メジャーリーグベースボール)でのスカウト経験を持つ著者が、MLBでの事例を元に編み出したチームビルディング手法である「アクティビティ」と「フォローアップ」について紹介しています。
組織におけるチーム作りへ応用できる実践的ノウハウとして、心理学を取り入れたコーチングやチームビルディングが解説されています。本書を通じて、メンバーの力を最大限に引き出すための結束力、主体性、部下育成などのベースとなる考え方を身につけられるでしょう。
宇宙兄弟(著者:小山宙哉)
『宇宙兄弟』とは、小山宙哉氏による宇宙を題材にした漫画作品です。主人公である兄・南波六太と、弟・日々人が、様々な問題に対して奮闘する様が描かれ、2012年には実写映画化とテレビアニメ化、2014年にはアニメーション映画が制作されました。
本書は、『宇宙兄弟』の登場人物やストーリーを題材にし、約20年にわたって3,000回を超えるチームビルディングを実施した著者による、チームビルディングに関する知見や方法がまとめられた一冊です。
「チームに恵まれていない」「チームビルディングをやりたいが、メンバーは興味を持ってくれない」「どのようにチームをまとめていいかわからない」とお悩みの方は必見。宇宙兄弟を知らない方でも、チームビルディングを楽しく学べるでしょう。
Good Team-成果を出し続けるチームの創り方–(著者:齋藤秀樹)
一般社団法人日本チームビルディング協会の代表理事である齋藤秀樹氏による一冊です。本書では、「病んでいる職場が劇的に変わる」チームビルディングの手法が紹介されています。 一時的に成果を出すような対症療法ではなく、チームとして成果を出し続けることのできる「Good Team(グッドチーム)」の創り方を、 意識改革の段階から解説されています。
「Good Team」を創るための原理原則を本書から学ぶことで、今後も成果を出し続けられる強固なチーム作りを目指してみてはいかがでしょうか。
リラックスと集中を一瞬でつくる–アイスブレイクベスト50-(著者:青木将幸)
チームビルディングには、ちょっとした時間で実施できるゲームやアクティビティが活用されることも少なくありません。会議や研修の場に緊張感が漂っている状況では、そのまま話を進めるよりも、チームビルディングを兼ねたちょっとしたアイスブレイクを実施することで、参加者をリラックスさせたり集中力を作り出せたりします。
本書では、プロのファシリテーターによるチームビルディング・アイスブレイクネタが、50個紹介されています。ネタの内容は主に学生や新社会人向けであり、新人社員研修や若手社員研修などで活用できるでしょう。
今日から使えるワークショップのアイデア帳–会社でも学校でもアレンジ自在な30パターン–(著者:ワークショップ探検部)
本書では、百戦錬磨のファシリテーター4人がチームビルディングに効果的なワークショップについて、所要時間や準備する物など、基本的な情報から具体的な手順まで詳しく解説しています。
身体を使ったワークから、キャリアの棚卸しができるワーク、社会課題やSDGsを自分ごとに落とし込むためのワークなど、さまざまな種類があります。
簡単なチームビルディングを会議に取り入れてみたい方から、本格的なワークショップをやりたい方まで、今すぐ試したいワークショップが必ず見つかる一冊です。
チームワーキング–ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方–(著者:中原淳、田中聡)
「チームを前に進めたいと考えているすべてのひとびと」に向けて書かれた本書では、「チームワーキング(Team+working)」と呼ばれる考え方を中心に、強固なチーム作りについて書かれています。
チームが陥るさまざまな失敗ケースが収録されていることからも、自分自身でその失敗ケースに対する自分なりの答えを出し、解説を受けることで、チームを動かす技術を学べる一冊となっています。
オンラインでもアイスブレイク! ベスト50-不慣れな人もほっと安心–(著者:青木将幸)
最近では、リモートワークの導入により、オンラインでのチームビルディングや研修を行う企業も増えています。しかし、オンライン上でのコミュニケーションは表情や声のトーンなどで相手の様子を伺うことが難しく、リアルとは異なるコミュニケーション能力が求められます。
本書では、そんなオンラインでの会議や研修の際に活用できる、厳選した50のゲームが紹介されています。Zoomをはじめとしたオンライン会議ツールに慣れながらのアイスブレイクや、オンラインならではのゲームなど、すぐに使えるネタを楽しく学べる内容となっています。
「オンラインでできるチームビルディングを探している」「オンラインでもチームでコミュニケーションをとりたい」という方におすすめの一冊です。
未来を共創する–経営チームをつくる–(著者:鈴木義幸)
本書は、チームビルディングに関する書籍の中でも、経営層やマネジメント層を対象に書かれているのが特徴です。20年以上にわたって、さまざまな企業のエグゼクティブをコーチングした経験を持つ著者は、本書で「会社は経営チームで決まる」と述べています。
その一方で、ハイパフォーマー(優秀な人材)がチームになるのは難しいという難点を挙げ、それを解決するために、本書は「なぜ『経営チーム』をつくるのは難しいのか」というトピックからはじまります。
そして、「チームの土台をつくる」「チームを進化させる」「強いチームをつくる個人となる」と、順を追って「経営チームが“チーム”になるため」の要点をひも解きながら書かれています。
チーム作りを経営層から考えていきたい場合には、有効活用できる一冊といえるでしょう。
チームのことだけ、考えた。–サイボウズはどのようにして「100人100通り」の働き方ができる会社になったか–(著者:青野慶久)
こちらは、東京都にあるソフトウェア開発会社「サイボウズ株式会社」の社長・青野慶久氏による著書です。青野氏が社長に就任した当時は、社員の離職率が28%にも上がり、社員の離職が続いていたという状況でした。そんな“ブラック企業”を“社員が辞めない変な会社”に変えたのが青野氏です。
本書では、青野氏の社長就任後から現在に至るまでの、サイボウズ株式会社の改変が書かれています。「多様性」を改変の軸に据え、社員一人ひとりが自分らしくあること、それに合わせた人事制度を増やすことで、現在では「100人100通りの働き方ができる」とまでいわれています。
サイボウズ株式会社の改変や、働き方への取り組みなどについて学びたい方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。
チームを変える習慣力(著者:三浦将)
本書は、累計20万部突破の「習慣力」シリーズの第3弾として出版された一冊です。主にマネジャー層の人材に向けて、コーチングのプロによる心理的安全性を高めるマネジメントを中心に書かれています。
マネジメントの悩みのほとんどは「人間関係の悩み」であり、それらを解決するたった一つの方法が「相手との位置関係を見直してみる」ことと本書で述べられています。
「メンタルコーチ」「人材育成のプロフェッショナル」「習慣力のエキスパート」などの肩書きを持つ著者による、メンバーのモチベーションが高く、活気あるチーム作りの秘訣について学べます。
心理的安全性のつくりかた(著者:石井遼介)
Googleによって行われた、生産性の高いチームの共通点を発見するための調査「プロジェクトアリストテレス」では、「心理的安全性」がチームの生産性向上の一つの要素であることがわかりました。
本書では、心理的安全性を理解し、心理的安全性の高い職場を再現できるようなアプローチについて、日本の心理的安全性を研究してきた著者によって解説されています。本書を通じて心理的安全性についての学びを深め、チームビルディングとして活用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
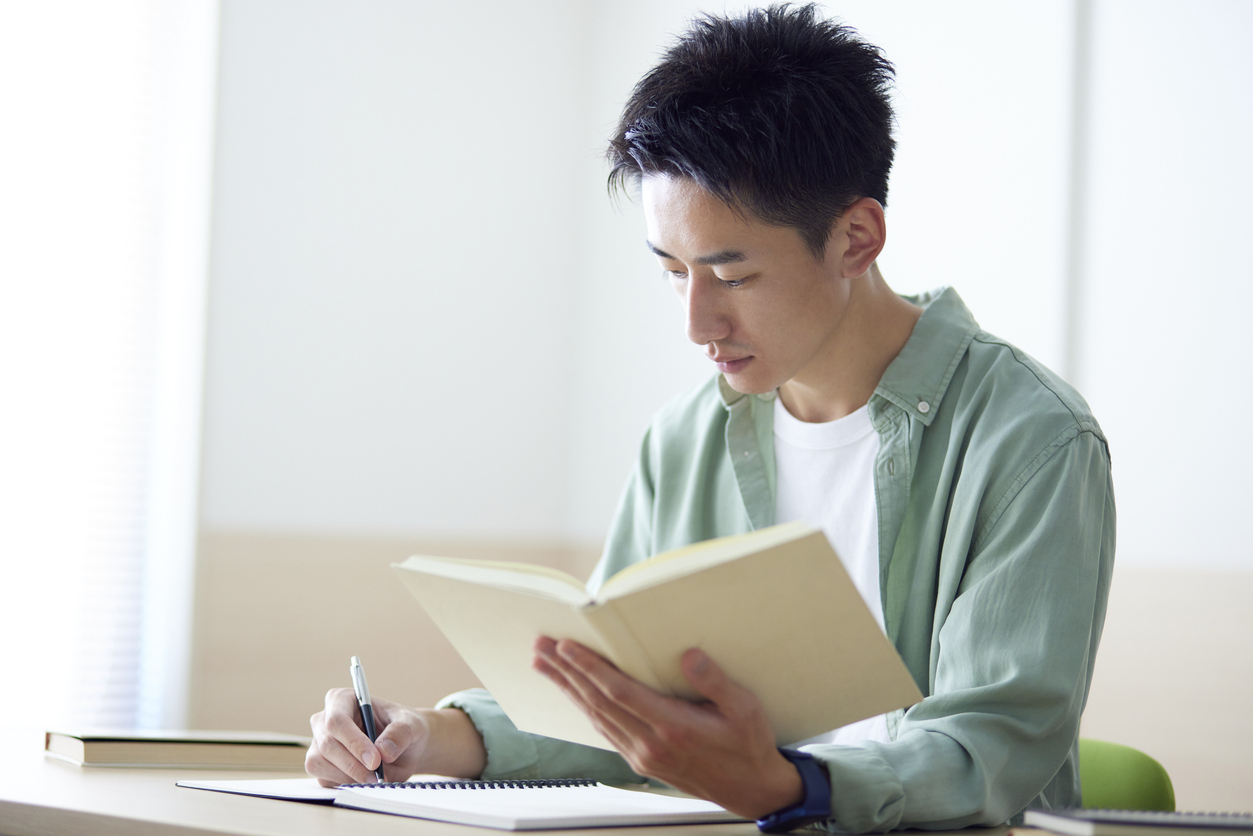
効果的なチームビルディングを行うには、まずは「チームビルディングとは何か」を学ぶことが大切です。ぜひ本記事で紹介した書籍を参考に、組織活性化に向けたチームビルディングを取り入れてみてはいかがでしょうか。
目次

ビジネスゲーム研修.comでは、研修のお役立ち情報や、体験型研修の事例をご紹介しています。オンライン研修やチームビルディング研修をお探しの方は、ビジネスゲーム研修.comにお任せください。